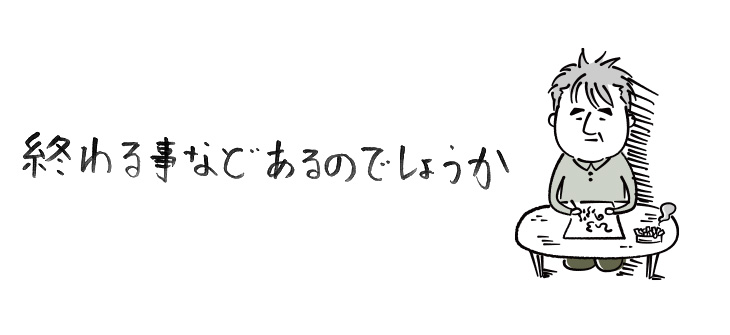
この連載のタイトルは「雑記」である。
最近は、この「雑記」に、何度か過去の思い出話を書いていたのだが、心ない人に「いい話を書くいい人と思われたがっている」と言われたり、椅子に画鋲を置かれたりとさんざんな仕打ちを受けている。
そんな「いい人おじさん」だと思われたいわけではないし、画鋲は尻ではなく壁に刺していただきたいので今後はもっと雑に書いていこうと思う。
べつに「いい話」を書きたいのではない。だが「書く」という行為は、あたりまえだが多くの場合「思い出す」という行為と直結している。なにか思い出さなければ、私はいま、たとえば目の前のキーボードの形状のことを書くぐらいしかない。
私が、なにか書くことのほかに続けていることといえば、写真を撮ることである。写真は、それ自体が見る価値のある「作品」になったりするわけだが、すべての写真が絵画のように発表されて飾られるわけでもないので、多くの場合「記録」として撮影される。そしてなんのための記録かといえば、やっぱりそれは「思い出す」ためなのである。
カメラをつくる会社、オリンパスのデザインセンター長である高橋純さんが雑誌のインタビューで言われていたことばに、とても感心した。
「写真に無駄な1枚はない。
今ここでパシャッと撮った1枚。
2、3日後に見てもつまらない。
2~3年後に見たら、ああこんなこともあったな
撮っておいて良かったなと思う。
そして、
10年後には驚きの1枚になっている」
記録と思い出の関係は、かくも流れ去った時間によって規定されるのだ。
今日はそんな写真にまつわる雑な話でもしよう。
私が初めてカメラを手にしたのは小学生の時。やはりカメラが好きだった父が、キヤノン AF35MLというカメラを買ってくれたのだ。もちろんフィルムカメラである。

これは、コンパクトだけれども明るい単焦点、つまり「ズームではない」「よくボケる」レンズのカメラだった。これが私の撮影のスタイルを決定づけた。「ズームできないから、大きく撮りたい時には撮りたいものに寄る」「撮りたいもの以外はぼんやりとボケているのが嬉しい」という写真に対する基本的な好みである。
その後、高校の入学祝いに、父の使っていたキヤノン AE-1に50ミリの明るい単焦点をつけたものを譲り受けた。このカメラは、まさにそれまで使っていた上記のカメラの一眼レフ版というか、同じ感触の写真がより本格的に撮れるマシーンであった。

1986年、高校1年生の私が、このカメラとレンズではじめて人間を撮った1枚がこれだ。

カメラの前に座ってくれたのは、同級生の女の子だった。ここから私の「綺麗な女の人がいたら、レンズを向ける」という人生が始まったのだ。

フィルムはコダックの「TRYーX」というやつで、現在の、いくら撮ってもコストがかからないデジタルカメラとはちがって、フィルム代も現像・プリント代も大変だったのだが、とにかくたくさん撮った。
たくさん撮り続けて、この日から31年。機材はすっかりデジタルになった。わたしも16歳から47歳になった。写真もすっかり・・・


・・・なんも変わってへんやんけ。やってることが一緒だ。撮りたい構図の好みの感じ、撮りたくなる女の人の好みの感じ、なんにも変わっていない。進歩がないといえばそれまでだが、ある写真家が私の撮ったものを見て言った。
「これは【生理】だから、ずっとこれをやるしかない」
写真家の名前は、宮本敬文といった。
「ヒロノブさん、ためしに僕をいま撮ってみて」

「ほら、ヒロノブさんの写真は、頭のてっぺんが切れてるでしょ。これはね、その人に近づきたいんだよ。でね、これぐらい視界いっぱいに人の顔を見るのはさ、人間、キスするときだけなんだよ。ヒロノブさんは、だれかとキスをするように写真を撮っているんですよ。それがその人の【生理】なんですよ。文章でいうと、【文体】だよね」
さっきの写真に収まってもらった女性、夏生さえりさんが聞いたら迷惑な話だが、たしかにそうなのかもしれない。綺麗な女の人に限らず、男性であろうと、動物であろうと、私の写真は「キスしてほしい」というあからさまな関係性への希求なのかもしれなかった。
それは「記録」であることは間違いないが、その時の心の動きそのものを削り取って、いつか必ず「思い出す」未来のためだ、写真家はそうも言った。
宮本敬文とはそれから10年以上に渡り、会うたびになにかにシャッターを切り、お互いの写真を撮り、撮ることについて果てもなく話した。いまここで撮ること、関係に欲望すること、そして思い出すこと。終わる事などないと思えた、生きることを生きる時間は、しかしある日、暗幕が降りるように、さっと消えた。
もうすぐ、この世界に彼がいない2度目の夏がやってくる。

何の気なしの別れ際、手を振る男にレンズを向けた。

最後まで、頭のてっぺんは切れていた。
『思い出したら、思い出になった。』これは、糸井重里さんのことばだ。
私たちは、なにかを思い出すために生きている。そうでなければ私の目の前にあるものは、いま、キーボードだけなのだから。

 更新日: 2025.01.15
更新日: 2025.01.15 



