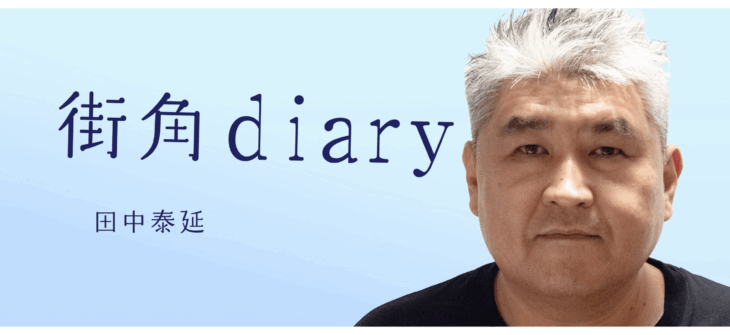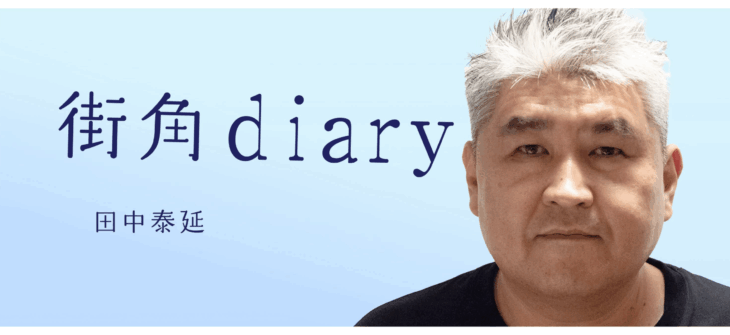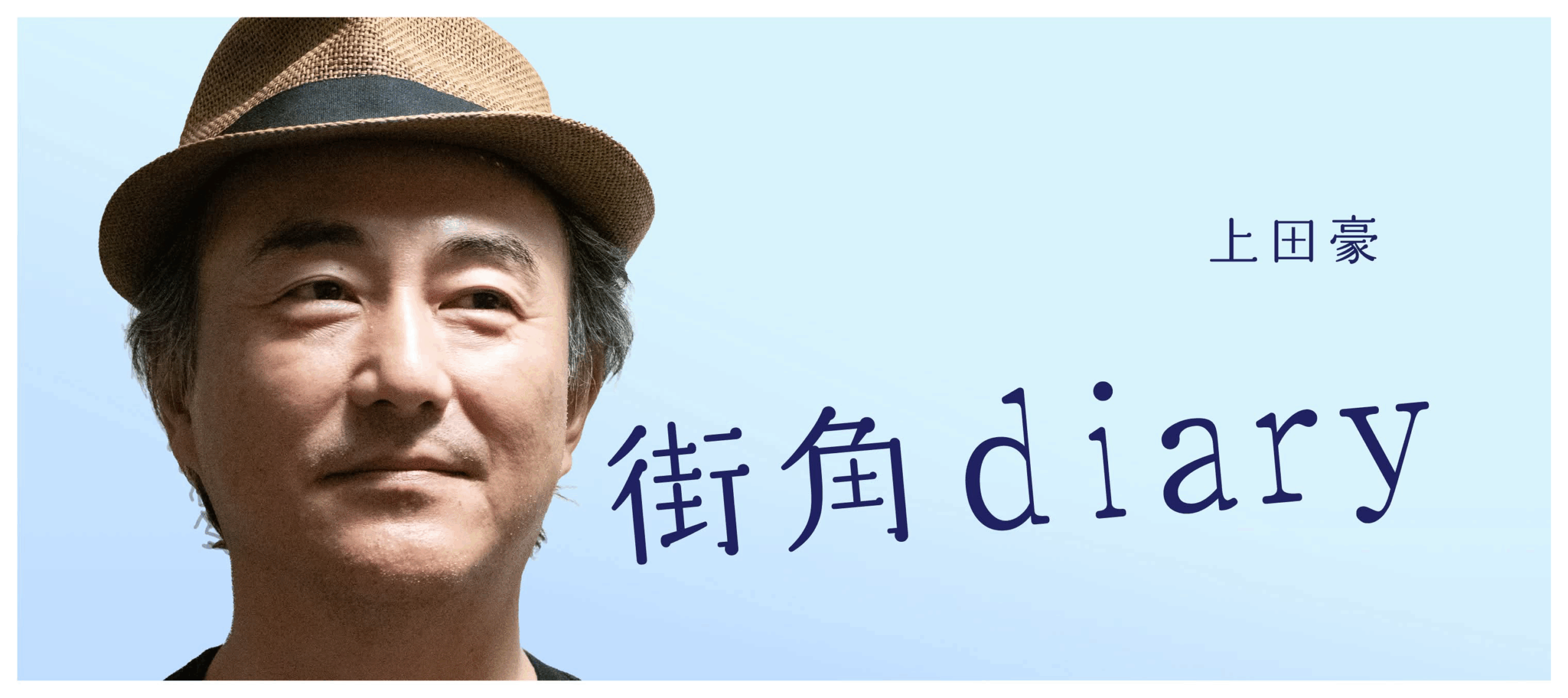
どうでもいいクリスマスの話
1975年12月24日。
6歳。
この世にサンタクロースなんていないのは知っていた。
世の中の慣例でこの日は親が子供にプレゼントを贈る日なのだと思っていた。
クリスマス数日前のことだった。
朝、小学校に行く前に、広告業界で仕事をしている毎晩帰りの遅い父からクリスマスプレゼントは何が欲しいかを問われた。
野球を始めて一年にも満たない俺は迷いなく「読売ジャイアンツのヘルメット」が欲しいと伝えた。
前の年に背番号1のついた読売ジャイアンツのユニフォームを買ってもらった。といっても特に王貞治選手のファンだったというわけではない。たまたま有名だった王選手のそれを欲しがっただけだ。
本当は高田繁選手が好きで彼のような青いグローブが欲しかった。でもそれをねだることはしなかった。すでにグローブを持っているのにそれをねだったところでその願いは叶わないと思ったからだ。
そもそも学校が終わってから毎日のように友達とやる野球では、ヘルメットなんて別に必要じゃなかった。それでもユニフォームを持っている以上、どうしてもヘルメットがないと格好がつかない。
*****
クリスマスイブ。
当時住んでいた団地の同じ階には、俺と同い年や年が近い子供がいる家庭が多く住んでいた。そのなかでも懇意にしていた、父と同じ広告業界で活躍するカメラマンの家でクリスマスパーティをすることになっていた。
クリスマスの雰囲気に飾られた部屋。テーブルに広がる料理。クリスマスツリー。招かれた近所の親子たち。広いとは言えない団地のダイニングでパーティが始まった時間に父の姿がなかったのはうちだけだ。始まってすぐ、他の子供たちはそれぞれの親からプレゼントを貰い、あちこちから喜びの声が上がっていた。それを俺も弟もただ見ているだけだった。
二歳違いの弟がポツリと言った。
「プレゼントってサンタさんがくれるんじゃないの?」
「ああ、サンタクロースからのプレゼントは別なんだよ?」
「ふ〜ん。パパやママはプレゼントくれないのかな」
「くれると思うよ」
「サンタさんも?」
「普段いい子にしてないとサンタは来ないって言ってたじゃん」
「じゃあ来るね」
「どうかなあ」
そのやりとりを見ていたのか「もうすぐお父さんが帰ってくるよ」と母が俺たちに声をかけた。しかし俺はその言葉が気休めだと思いあまりあてにはしていなかった。パーティの最中に父が現れてプレゼントを渡してくれるなんて想像できなかったからだ。俺たちが寝る前の時間に仕事から早く帰って家にいることなんてほとんどなかった。
呼び鈴が鳴った。
カメラマンの奥さんが玄関の扉を開けた。
「こんばんは」と聞き慣れた声に、ついダイニングから玄関の方を覗き込むと父がそこに立っていた。手には大きな紙袋が下げられていた。
弟は欲しかったプレゼントを手にして大喜びだ。
そして俺はジャイアンツのヘルメットを受け取った。
「ヘルメット、両耳がついてるものと片耳のものがあったけど、やっぱり片耳の方が格好いいからそっちを買ってきた」と父は少し誇らしげに言った。
「ありがとう。よかった片耳で。プロ野球で両耳のヘルメットを被ってる選手なんていないよ」
ヘルメットを手に入れた喜び以上に、仕事から早く帰ってきて約束を果たしてくれた父の気持ちがとても嬉しかったような気がする。
みんなでケーキを食べ、21時頃にクリスマスパーティが終わった。
会場の家から数部屋離れた自宅に帰る。
なんだかよくわからないけど「尊さに触れたような気持ち」と「一生懸命練習してもっと上手くなって絶対プロ野球選手になるという決意」と一緒に、YGマークの入った黒いピカピカのヘルメットを抱いて布団に入った。

希望に満ちた野球人生が始まった。
*****
1985年12月24日。
16歳。
バイト先の居酒屋はいつも以上に賑わっていた。
店のある駅前のビルも周りの商店街もクリスマスの雰囲気に飾られていた。道ゆく人々や店内の客、特にカップルは浮かれているかのように夜を楽しんでいた。
この店に採用された理由は単純明快だった。
後に店長に聞くと、履歴書に「武道の有段者との記載があった」のが決め手だったらしい。酔客のトラブルの際に役に立つかもしれないと思ったからだと笑って言った。ただ、この日まではそんな場面が来ることは一度もなかった。
バイトの高校生は夜9:00までの勤務という話だったが、連日25時過ぎまで働いていた。それが嫌だと思うこともなく、翌日が学校でも気にしなかった。むしろ目の前の仕事に没頭しなくてはならない時間が有り難かった。
野球の道を諦めざるを得なくなってから2ヶ月も経つというのに、気持ちは荒れたままだった。心の整理なんてつくはずがなかった。野球という二文字を見ることも辛い日々。生きる希望を失ったまま、暗闇の中をただひたすら独りで歩いているような感覚が離れなかった。
何もない俺にとって、昔の地元の仲間や不良仲間と過ごすこと、そしてバイトに没頭することだけが煩わしい全てから逃れることのできる術だった。
25時過ぎ。いつものようにバイトが終わった。
クリスマスだからと店長がフライドチキンを持たせてくれた。
冷たい風が吹く中、自宅まで自転車で帰らなければならない。客に飲まされた酒で少しふらつく足元が覚束ないまま、駅前の商店街から少し外れた路地にある駐輪場へと向かう。
駐輪場に差し掛かった時、屯ろしている三人の男たちが視界に入った。
*****
寝静まった家族を起こさぬよう、極力物音を立てないよう自宅の部屋に入った。
部屋の灯りを点け、着ていた革ジャンをベッドに放り投げると鏡を覗き込む。右の頬が少し腫れ、口元には少し血が滲んでいた。拳を見ると相手の歯で切れたのかざっくり切れ血がこびり着いていた。貰ったはずのフライドチキンを投げつけた記憶が蘇った。
ふと、机の上を見る。
一枚のレコードが置いてあった。

矢沢永吉「Ten Years Ago」
先月発売されたばかりのアルバムだ。
まさか、これ、クリスマスプレゼントか?
数日前、「おまえ矢沢永吉好きだったよな?」と父に聞かれたことを思い出した。
腫れ物を触るかのように話しかけてきた父が煩わしかった。希望を失い荒んでいく息子に対してどうにか会話の糸口を見つけようとした父の気遣いは感じていた。その煩わしさの原因が自分自身の情けなさだということもわかっていた。それでも顔を合わせると素直に向き合うことができなかった。
暗闇の中で独りの日々。親と話すことすら煩わしくあの時も無愛想な返事をした。差し伸べられる手を払うようなことばかりしていた。
レコードを手に取る。
キャロル時代の曲を新たにレコーディングし直したアルバムだった。
鶴田浩二や高倉健のレコードが似合いそうな父が、わざわざレコード屋まで行ってこのアルバムを買うシーンを想像すると少し可笑しかった。
ふと、アルバムのタイトルに目が止まった。
Ten Years Ago。
10年前の自分を思い出せってことか? と思いながら、俺はそのタイムマシンをレコードプレーヤーに乗せ、ステレオの音量を最小にしてベッドに潜り込んだ。
レコードが回り出し、一曲目の曲が流れてくる。
I’m a lonely boy
恋しくて
Come home tonight
君がいればすべて
OK OK
I’m a lonely boy
淋しくて
Come home tonight
愛があればすべて
OK OK
一人でいるのはつらい
気持ち I feel blue
涙で抱きしめるなら
I’m feel so good
君だけさ
流れてきたのは「ホープ」という曲だった。
(作詞:大倉洋一 作曲:矢沢永吉)
なぜか目の前が滲んでいった。
上田 豪 広告・デザイン/乗り過ごし/晩酌/クリエイティブ
1969年東京生まれ フリーランスのアートディレクター/クリエイティブディレクター/ ひろのぶと株式会社 アートディレクター/中学硬式野球チーム代表/Missmystop