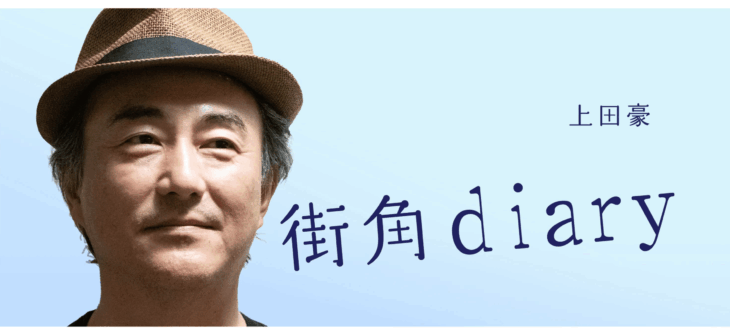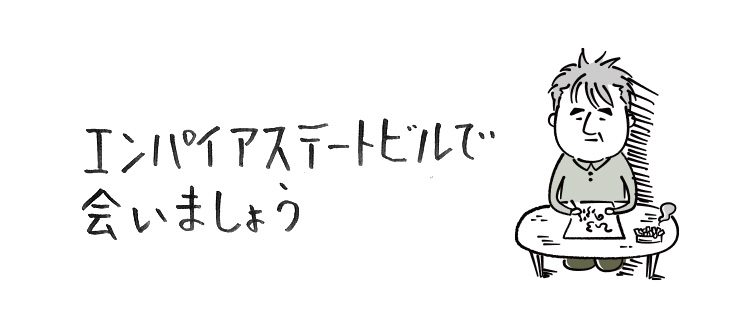邦画実写史上、売上、観客動員数ともに22年ぶりに記録を塗り替えた『国宝』。(※)
この大ヒットを受け、2026年2月からは全米での公開も予定されています。
歌舞伎という、決してマジョリティとは言えない題材でありながら、この大ヒットの理由はいったいどこにあるのでしょうか?
※ 2025年12月21日時点で、観客動員1,286万人、興行収入181.4億円(出典:映画.com)
2025年6月からの上映で、巷には多くのレビューが溢れています。内容も多種多様。僕も観た直後に、拙い感想文を書きました。ちょっと恥ずかしいですけど、以下に貼り付けさせていただきます。
映画『国宝』を観た僕に「緊張の伝染」が起きた理由
ファーストキスの記憶。
誰にとっても忘れられない青春の思い出。決して汚されたくない、淡くていつまでも色褪せないひとコマとして大切にしている人も多いと思う。
僕は今日、心のずっと奥の方にしまい込みすぎて、もはやカビの匂いすらするそんな思い出の宝箱を、数十年ぶりに開けることになった。遅ればせながら、映画「国宝」を観た。
もはや説明不要の大ヒット映画。
3時間、長い映画だ。でも僕だけでなく皆が映画に集中していたと思う。そう感じた理由は、普段は耳障りな誰かがポップコーンを食べる音が、全くと言っていいほど聞こえなかったことだ。
「国宝」は役者の息づかいだけでなく、衣装がすれあう音や小道具をそっと置く音などに、自然と耳を澄ましてしまう映画だ。きっと会場中の皆がそのことを共有していたのだと思う。最も印象に残ったのは、まだ若く舞台経験の少ない2人の主人公が、初めて大きな舞台に立つシーンだ。ふたりはガチガチに緊張している。
僕個人の話をさせてもらうと、幼い頃からあまり緊張をしたことがない。
緊張は「準備不足」と「自分以上の自分を見せようとしている時」に起こるのだという。僕は子供の時から、準備万端で何かに臨める状況などあり得ないとどこか達観していた。さらに自身を冷めた目で俯瞰していて(早い段階から諦めている)、そのため自分に期待することもなく、たいして自分を良く見せようとしていない。緊張しない理由はそこにあるのではと自己分析している。
冒頭の、ファーストキスの前でも、僕は全く緊張していなかった。
でも、いざ、という時に急に鼓動が高鳴り、世界の輪郭がばやける感覚に襲われた。
理由は、その相手、当時付き合っていた彼女だ。
彼女の方が、その雰囲気を察してしまったのだろう、とても緊張しているのがわかった。本当に彼女の鼓動が聞こえてくるようだったし、呼吸のリズムも瞳の動きも落ち着かなかった。全て僕の未経験によるぎこちないリードのせいだったと反省している。
緊張は伝染する。よく言われていることだ。
彼女の緊張が僕にまで移り、キスする前に言おうとして用意していた(思い出すのも恥ずかしい)台詞も言えず、ほとんど記憶も残っていないのが、僕のファーストキスの思い出だ。
甘酸っぱい思い出を白く塗りつぶしたその緊張の伝染も、会社のプレゼンを前に固くなっている同僚や、バンドの演奏前に顔を白くしている友人を見ても起こらない。常に引き起こる現象でもないらしい。しかし。
主人公を演じるふたりが舞台袖で緊張に支配されているのを見て、僕の身体は震えた。緊張しているのがわかった。まるで今から自分が多くの観客の前に立つかのような恐怖を、はっきりと感じていた。歯がガタガタ鳴りそうになるのを、奥歯に力を入れて必死で耐えた。
圧倒的な感情移入。
映画を見ただけの僕になぜここまでの感情移入が起きたのか、映画を見終わって冷静に振り返ることができる今だからはっきりとわかる。僕はこの映画の最中、ずっと2人の主人公に、恋をしていたのだ。
うーん、よく恥ずかしげもなくこんなこと書けたなと今にして思います。ファーストキスだなんて、あーた、いったいいつの記憶引っ張り出して来たんですかって話ですよ、奥さん。
申し遅れました、わたくし渡辺拓朗と申します。普段はフツーのサラリーマンをしています。そして、副業でライター業をかじっております。
なぜに突然名乗り出たかと申しますと、これから再度、映画『国宝』のレビューを書かせて頂きますが、どうしても僕自身とリンクした内容に帰結してしまう気がしたからです。そのため、僕の身上を公開した上で読んで頂くのがせめてもの礼儀だと思ったからです。この映画、そのどうしても自分自身と重ねて考えてしまうことこそが、大ヒット要因のひとつなのではないかと考えています。
なにせ1,200万人を超える人がこの映画をすでに観ています。観た人の数だけ感想があることは承知しています。それでもきっと、どこかの場面で何かしら、誰もが自分と重ね合わせた感想を得るのではないでしょうか。そんな映画だと思っています。
初回レビューに決定的に足りなかった視点
恥を忍んでなぜに初回に観たレビューを貼り付けたのか。そこには明確な理由があります。この映画には決して避けて通ることのできない重要なテーマが存在します。
映画を観た方であればすぐにわかると思いますが、「才能か血筋か」です。歌舞伎という世襲の世界に、全くの外界から飛び込みその才能を開花させる吉沢亮演じる立花喜久雄。一方、歌舞伎の家に生まれたことで、自分の意思とは関係なく歌舞伎役者の宿命を負った横浜流星演じる大垣俊介。ふたりのライバル関係こそが、この映画の骨格であることは疑いようがないと思います。映画の監督を務める李相日と主演の吉沢亮とのインタビューにおいても、はっきりと「才能か血筋か」がテーマであることを明言しています(2025.6.17 新潟日報)。
僕ももちろん、映画を観てそのことは理解できました。でも、あえてそのこと以外でレビューを書いたのです。理由は、すでに他の多くの人がそのことに言及したレビューを書かれていたこと、です。同じ内容など、書く必要がないと判断してのことでした。
でも、僕は知っていました。知っていたも何も、自分自身の心の中の声を聞こえぬふりをしていたのです。「才能か血筋か」のメインテーマを語ることから逃げていた、そう言い換えることもできます。
なぜなら、あのレビューを書いて以来、僕の心の中には、ずっと消えない罪悪感にも似た薄黒い何かが、うごめき続けているのです。このテーマと面と向かって自分なりの答えを出さない限り、僕は前に進めないのではないだろうか、そんな強迫観念に駆られるまでになりました。
僕もライターを名乗る端くれです。書く対象から目を逸らすようでは、ペンを取る資格すらありません。
そう思うと、僕の足は再び映画館に向かっていました。
そんな僕が、『国宝』、再び。
いったい、僕は何を感じて、どんな考察を導き出せるのでしょう。
今回は映画の一部を深く掘り下げなければ、決して出すことのできない答えを求める思考の旅です。ネタバレ全開で行きますんで、よろしく!
才能VS血筋
まずこの問いに対して、僕が1度映画を観た時点で抱いた感想は「どっちも大事なんじゃね?」という極めていい加減なものだったことを告白しておきます。いくら歌舞伎の家に生まれても、全くの大根役者であったのであれば、当然観客はそっぽを向いてしまうだろうし、何より何百年もの間、観客を熱狂させ続けることなどできっこないと思うのです。このことに対して、異を唱える方は少ないのではないでしょうか。
では突出した才能のみがあった場合はどうでしょうか?
それに関しても、僕はやはり血筋も大切なのでは、と思っていました。歌舞伎界が世襲で数百年続いてきたことが何よりの証拠となりますし、徳川15代だって、天皇家だって、大切なのはその純血たる筋だとされて来たはずです。
実際に、映画『国宝』においても、この「才能」と「血筋」に主人公たちは翻弄され続けます。俊介は父である花井半次郎が交通事故に遭い代役が必要となった際に、当然自分にその大役が回ってくるものだと確信していたに違いありません。その代役がよそ者の喜久雄に決まった時の俊介の気持ちを推しはかると、胸が潰されそうになります。実の父は、自らの大切な代役に喜久雄の「才能」を選んだのです。
また、喜久雄も自分が歌舞伎の「血筋」と、無縁であることでこうむる不条理に苦しみます。半次郎なき後、後ろ盾を失った喜久雄はたいした役も貰えぬ境遇に、自らに流れぬ歌舞伎の血をどれだけ欲したのか想像に難くありません。
「才能」でも「血筋」でもないのだとしたら、いったい何が必要なのでしょうか。再鑑賞の焦点は、この1点に集中したいと思います。
2度目の鑑賞でもやっぱり響いたあの言葉

上映開始から4ヶ月が過ぎたのにもかかわらず、その日の映画館の座席は、8割ほど埋まっていたように思います。若い人も多く見受けられます。本当に多くの世代に観られているのだと、現場感覚で実感しました。
内容も全てわかっているのにもかかわらず、僕は再度主人公たちと同じ緊張感に縛られ、運命に翻弄され激しく揺れる人間ドラマに心を痛め、主人公たちの一挙手一投足に、やはり恋に落ちました。美しい映画です。老若男女問わず、観るものをうっとりとさせます。3時間の長い上映時間、僕はいったいこの映画のどこに惹きつけられたのでしょうか。
僕は、最初の鑑賞の時にすでに胸に響いていたある単語が、再度大きく響き渡るのを確信しました。
その言葉は、「覚悟」です。
「お前に覚悟はあるのか?」
「お前の覚悟とはなんだ?」
「お前の覚悟を決めよ」
映画で「覚悟」という単語が発せられるたび、空耳だとわかっているそんな問いが、どこからともなく僕の頭に不思議と響いて来たのです。
「血筋」の重圧と「才能」に対するコンプレックス
自分から逃げるように歌舞伎界から姿を消した俊介。対して、追われるように梨園をあとにした喜久雄。立場は違えど、ふたりとも己が抱えるコンプレックスに耐えきれなくなった結果だ、と感じました。
まずは、後から来た喜久雄に父の代役を取られ、喜久雄の「才能」にコンプレックスを感じた俊介の場合です。
俊介が、歌舞伎の家に生まれただけで、全くその才能もなく努力も怠り続けていたのであれば、この映画は決して成り立たなかったはずです。映画に描かれている限り、俊介は喜久雄と共に学校が終われば一目散に稽古に向かい、そこで厳しく指導を受けていました。初めて喜久雄と共に演じた「二人藤娘」や、京都南座でメジャーデビューを果たした演目「二人道成寺」では、決して喜久雄に引けを取らず堂々と舞い、僕はまさに長い歴史の血を継ぐ賜物だと感じていました。俊介は喜久雄というライバルとともに、切磋琢磨して歌舞伎役者への道を順調に歩んでいるように見えました。
しかし、父半次郎が演じる予定だった「曽根崎心中」のお初の代役が喜久雄に決まり、その晴れ舞台を客席で観ていた俊介は、逃げるように演目の途中で会場をあとにします。
「俺は逃げるんちゃう」と、泣きながら力無く歩く俊介の後ろ姿に、僕は大好きなマンガの一場面を思い出しました。
それは松本大洋が描く『ピンポン』です。
卓球に賭ける高校生を描いたこのマンガの主人公はペコ。子供の時からずっと卓球で一等賞の存在でした。ライバル役として描かれるのは、そんなペコの陰に隠れた目立たない存在のスマイルです。
ペコは自分の才能に甘え、練習嫌いで部活もサボりがち。対してスマイルは、顧問とのマンツーマン指導によってその能力を覚醒させます。いつの間にか逆転してしまった力関係に、ペコは卓球から足を洗うのです。ずっと自分より下だと思っていたスマイルに、勝つことができないとわかった時のペコの表情は、寂しさを感じさせるものでした。
今回、2度目の鑑賞で気がついたことが、俊介の場合、ペコよりも苦悩する理由がひとつ多くあったことです。それが「血筋」です。「才能か血筋か」に重きを置いて鑑賞したことで得た、新たな観点でした。
両親だけでなく、一家を取り巻く人々はもちろん、観客だって花井半次郎の跡取りは俊介だと、そう思っていたはずです。そして何より俊介自身も、父の代役は自分であると、心のどこかではそう確信していたのではないでしょうか。それが「血筋」に縛られた俊介の宿命だったという前提を、1度観た時の僕は素通りしていました。
その前提がボロボロに崩れ去ったのです。僕はあの場から逃げ出した俊介の後ろ姿に、責めるどころか愛おしさすら感じて、滲むスクリーンを見つめていました。2度観たことで生まれた深い共感でした。
「血筋」を求める喜久雄と天下人の類似点
映画『国宝』では美少年として描かれている喜久雄と、「サル」の愛称で知られる天下人の「豊臣秀吉」に、外見上の類似点を見つける方が難しいかもしれません。
『国宝』を一度観ただけでは、僕はとても秀吉を引き合いに出そうだなんて考えませんでした。でも今回、「血筋」に焦点を絞って観た結果、ふたりの決定的な共通項が浮き彫りになったのです。
高校教育で一般的に使用されている教科書、山川出版社『詳細日本史』では、秀吉について「低い身分から身をおこし、織田信長の家臣となって武功を立て、ついには信長のあとをついで全国統一を達成した」と記述されています。僕が子供の頃に読んだ日本の歴史を描いたマンガでは、秀吉は農民出身とされていました。ボロ切れを纏って竹槍を持った猿顔の男が描かれていました。2026年の大河ドラマ『豊臣兄弟!』でも、池松壮亮によって泥臭く演じられています。

最近では研究の進展でその出自に不明点が多く見つかり、「低い身分から」との記述にとどめてあるのが通例のようです。しかし農民にせよ下級武士にせよ、他に類を見ないほどの出世街道を物語るのに大きな差はありません。
ここまで書けばお気づきの方もいると思います。そう、秀吉にも「血筋」がないのです。そのことに、秀吉自身、相当のコンプレックスを抱いていたはずです。その証拠のひとつがこちらです。

これは2024年に見つかった、信長の家臣たちが連名で秀吉に送ったとされる書簡の写しです。これによると、秀吉は「三木合戦(1578〜1580)」や「鳥取兵糧攻め(1581)」の自らの武功を、何人もの信長側近に一斉メールしていたようです。同じ内容を何枚も複製させ、わざわざ同僚たちに送りつけていたのです。聞いてもいない手柄自慢に対して、困った同僚たちは連名で「いやさすがっすね、マジ半端ねーっす」と返信したのがこの書状とのこと。
当時最大の関心事である戦の勝敗など、数日のうちに早馬が伝えたはず。「いや、わざわざ手紙にしてこなくても知ってるっつーの」的な内容を秀吉が送りつける背景には、やはり自らが低い身分の出自であるコンプレックスが隠されていたからに違いありません。常に活躍し続けなければ、他の武将たちより早く転落してしまうことを恐れていたのだと思います。
また、秀吉には多くの側室がいたとされます。『日本史』を著したルイス・フロイスの目には300人もの愛人がいたように映っていたようです。記録に残る側室たちは、「前田利家」の娘など名家の女性ばかりが目立ち、これも秀吉の「血筋」に対するコンプレックスの現れだと推測できます。中でも最たる例は「茶々(後の淀殿)」であり、元主君「織田信長」の姪に当たります。秀吉にとって織田家の「血筋」は喉から手が出るほど欲していたものに違いありません。

似た場面が、映画『国宝』にも登場しますよね?
「喜久雄兄ちゃん」と無邪気に話しかけてくる森七菜演じる「彰子」、彼女は歌舞伎界の大物で、演目の配役にまで影響を持つ「吾妻千五郎」の娘として登場します。物語で新キャラが急に出てくる時は、その後の急展開に繋がることが多いもの。『国宝』でも場面が切り替わると、ホテルの一室で喜久雄がさっそく彰子に覆い被さっていました。
なにしとんねん。
最初の鑑賞での素直な感想です。先代が亡くなってからたいした役も貰えず腐りかけていた時期だからって、歌舞伎界の大物の娘にそんなことしたらそりゃそうなるよと思いました。その後のあれよあれよの転落劇。目も当てられませんでした。
でも「血筋」に注目した2度目の鑑賞では、喜久雄の行動理由がとてもよくわかりました。父親を殺され、たったひとり歌舞伎の世界に飛び込んで以来、喜久雄はずっと「血筋」をうらやんでいたはずです。
三浦貴大演じる「竹野」が発した「歌舞伎なんてただの世襲だろ」という言葉に対して、鬼の形相で食ってかかったこともあれば、半次郎の代役として舞台に上がる直前には「血が欲しい」と素直にこぼしたこともありました(この時、俊介は「お前には芸(才能)がある」と返しています)。喜久雄はずっと自分に歌舞伎の血が流れていないことに大きなコンプレックスを抱いていたのがわかる行動です。さらに歌舞伎界を去る時には「結局歌舞伎は血や。芸なんか関係あるか。血筋や!」とずっと溜め込んできたであろう本音を吐露するシーンもありました。
天下を獲りこの世の春を謳歌していた秀吉でさえ、最後まで「血筋」のコンプレックスを拭いきれなかったのです。30歳以上も歳の離れたまだ10代の茶々を、見栄も外聞もなく我が物にしようとした歴史的事実は、喜久雄が彰子に取った行動に対して、僕に一瞬の理解を与えました。もし僕が喜久雄であっても、同じ行動を取るかもしれない、そう思い直すまでになりました。
「才能」でも「血筋」でもなく、どさ回りでふたりが見つけたもの
俊介も喜久雄も、歌舞伎界を去ったあと、同じような境遇でひっそりとどさ回り営業を続けます。逃げ出した俊介と、居場所を失い追われて出ていった喜久雄の違いはあれど、ふたりとも憎み、絶望した歌舞伎で生計を立てていたことが皮肉です。彼らはなぜ歌舞伎を続けたのでしょうか?
僕はこのふたりの選択は、田中泯が演じる人間国宝「小野川万菊」の言葉にヒントが詰まっているのではと感じました。
「あなた歌舞伎が憎くて憎くて仕方がないんでしょう? それでもいいの。それでもやるの。それでも舞台に立つのが、あたしたち役者なんでしょうよ」
生まれてこの方、歌舞伎以外の世界に触れたことのない俊介。
父親を殺されて以来、人生の全てを歌舞伎に捧げてきた喜久雄。
ふたりには、歌舞伎しかないのです。頭で考えるより先に、心で思うより先に、身体が勝手に踊り出す。その悲しい習性を認めた時、彼らは「才能」でも「血筋」とも違う、芸に対する新たな姿勢を身につけたのではないでしょうか。
俊介は「血筋」という逃れられない宿命の中で、それに応えることのできない自分の価値を見失い、その世界から身を引きました。一方で喜久雄は「才能」という恵まれた資質ゆえに、血筋を持たぬ自分の存在理由に迷いました。
ふたりの苦悩は正反対のようでいて、本質的には同じものです。どちらも「与えられたもの」だけに囚われ、まだ「自分で選び取ったもの」を持っていなかったのです。このどさ回りを通じて、ふたりがようやく掴むのが、もうひとつの大切な軸となります。
それは、「才能」でも「血筋」でもなく、自分自身を芸に差し出す決断です。
逃げ出したことを素直に認め、世間の嘲笑に耐えてでも、血筋の持つ宿命を全うする俊介の「覚悟」。
よそ者、と揶揄する周りの雑音をシャットアウトして、ただ芸にのみ精進する喜久雄の「覚悟」。
何物にも負けぬその言葉の力強さこそが、2度の鑑賞で、「覚悟」という言葉が僕の中でずっと響き続けた理由だと思うのです。お初と徳兵衛をふたりで演じた「曽根崎心中」で、繰り返される「覚悟」という言葉。それはただの台詞ではなく、彼らの「生き様」として伝わってきた、そう感じたのはきっと僕だけではないはずです。
「才能」だけでは限界があります。「血筋」だけではなんの説得力もありません。そこに「覚悟」が加わって初めて、本物の結晶として輝くのです。
そしてこの答えこそが、『国宝』という映画が描く、「才能」か「血筋」か、の問いに対する到達点なのだという解を得ました。
なぜ僕に、「覚悟」という言葉が響くのか?
「お前に覚悟はあるのか?」
「お前の覚悟とはなんだ?」
「お前の覚悟を決めよ」
映画の後半、壮絶に歌舞伎を演じるふたりの「覚悟」の眩しさに目を細めながらも、不思議とそこに自分の姿を重ねていました。
『国宝』で「覚悟」という台詞を聞くたびに、僕に呼びかけるように聞こえた幻聴の正体はなんでしょうか?
正直に白状すれば、僕には思い当たる節があります。
そう、最初に書いたレビューです。
僕は『国宝』を公開からかなり遅れて鑑賞しました。すでに多くのレビューや考察がSNSを中心に出回っていた頃です。僕は、それらと同じ舞台に立つことから、逃げたのです。
確かに、レビューに書いたように、主人公たちの緊張の伝染に強い衝撃を受けたことは事実です。でも、僕にとって、本当に心を揺さぶられたのは、そこだったのでしょうか?
違います。即答できます。
先に言及した通り、一回目の鑑賞の時点で、あの幻聴が僕にははっきりと聞こえていたのです。僕は耳を塞ぎ心を閉ざして、映画の後半、必死に自分自身に言い聞かせていました。
「僕ハ他ノ人タチト違ッタ感性ノ持チ主ダカラ、感想モ他ノ人タチト違ッテ当タリ前ナンダ」
その言葉は、ずっと虚しく響き続けました。
自分が一番よくわかっていたのです。
僕には「才能か血筋か」という、この映画最大のテーマに真正面から向き合い、考察し、文字を綴る「覚悟」が欠落していたのです。
こんな僕が、ライバルの「才能」に己の敗北を認めることもできず、10年以上も姿をくらませていた俊介を、嘲笑うことができましょうか?
全てを「血筋」のせいだと不貞腐れ、労せずそれを手に入れようと目論んだ喜久雄を、馬鹿にすることなどできましょうか?
きっと、巷に溢れるレビューに、自分のレビューで立ち向かうことが怖かったのだと思います。自分の思考を公開することで、人前で裸になる勇気がなかったのだと思います。
全ては、僕に「書く」ことの「覚悟」ができていないからだ、そう自分自身で、やっと認めることができました。
僕に「書く」ための「覚悟」が備わっていなかった、もうひとつの証拠があります。
それは、僕が文章の師と仰ぐ3人のライターの言葉を、全く理解できていなかったことです。
佐藤友美さんは著書『書く仕事がしたい』で次のように述べています。
文章を書くことは、確実に「世界を狭める」ことだとも思っています。
『書く仕事がしたい』佐藤友美(CCCメディアハウス(現CEメディアハウス) 2021年)
近藤康太郎さんの著書『三行で撃つ』の裏表紙には、こう書かれています。
文章は、見えていたものを見えなくすること。
『三行で撃つ』近藤康太郎(CCCメディアハウス(現CEメディアハウス) 2020年)
田中泰延さんも『読みたいことを、書けばいい。』で、丸々1ページを使って、次のひとことだけを記しています。
書くことは世界を狭くすることだ。
『読みたいことを、書けばいい。』田中泰延(ダイヤモンド社 2019年)
僕は、「書く」ことは自分の世界を広くするものだ、そう思っていました。3人の著書を読んだ後でも、それが覆ることはありませんでした。きっとそのことの真意を、本気で考えたりもしていなかったのだと思います。
『国宝』を2度鑑賞して主人公たちの「覚悟」に触れ、僕なりに小細工せず向かい合った今、はっきりとわかることがあります。
僕が「書く」ことで世界を広げられると勘違いしていたのは、結局は読者目線の域を出ていなかったということです。お客さん気分が抜けてなかったのでしょう。書き手として、対象物と向き合い、正面から横から裏から下から上から見つめて、それでもわからずに近づいてみたり離れてみたり、そこまで狂信的に「書く」ことに没頭できていなかっただけだ、そう気づいたのです。
佐藤友美さんは、書く対象物を一生懸命に知ろうとすることが大切だとした上で、こう続けています。
知ること。
『書く仕事がしたい』佐藤友美(CCCメディアハウス(現CEメディアハウス) 2021年)
知ろうとすること。
それは、ほとんど、愛することに近いと思います。
Love is blind.
書くことは、世界を狭める。
僕は書き続ける〜なんのために「書く」のか
僕は世界を狭くしてまで、どうして書き続けるのだろう。
きっと、「好きだから」に他なりません。
今回僕は、田中泰延さんが講師を務める『「お金を払ってでも読みたいことを、自分で調べて書けばいい」と思える書く力の教室』を受講していました。次々と出される課題。初めて経験することも多く、難易度も高かった。
でも。
楽しかったんです。心から楽しかったんです。僕は書くことが好きだと再確認できたし、今まで使ったことのない文体にチャレンジして、自分の書いた文章で推敲中に何度も笑いました。
泣くことさえありました。苦しくて泣いたのではなく、自分の書いた文章に、嬉しくて泣いたのです。本当に幸せな3ヶ月でした。
僕は、ライターでお金を稼いでいるわけではありません。普通のサラリーマンとして、ある程度安定した収入もあります。この姿勢は、物書きとして、逃げの姿勢でしょうか。僕はこのことに対して、ずっと悩み続けてきました。
僕は「書く」ことが好き。好きなことを思い切り楽しむための免罪符として、僕はサラリーマンを続けています。書き続けるために必要な糧として、会社に通い続けているのです。でも、本当にそれでいいのでしょうか?
田中泰延さんは糸井重里さんから「ものを書くのであれば、コンビニかガソリンスタンドで働きながら書いた方がいい」と言われたそうです。
以前の僕は、その言葉をそのまま「文章を書いて食べていくのは難しい」程度にしか受け取っていませんでした。けれど今は、「本当に書きたければ、書くことにしがみつきたければ、なにをしてでも書き続けるべきだ」と、別の重さで受け取っています。そう思えたのは今回、僕に新たに芽生えた、書き続けると決めた「覚悟」のおかげだと、そう思っています。
もう、サラリーマンの自分に悩まない。
近藤康太郎さんは、どうして書くのか、について次の文章を記しています。
文章を書くのはなんのためか。ひとつだけここで言えるのは、いやしくもプロのライターなら、狭量と不寛容と底意地の悪さにあふれた、争いばかりのこの世界を、ほんの少しでも住みやすくするため、生きやすくするため、肺臓に多量の空気が入ってくるために、書いているのではないのか? そうでなければいったいなんのため、机にしがみつき、呻吟し、腰を悪くし、肩こりに悩まされつつ、辛気くさく文字を連ね、並び替え、書いては消し、消しては書いてを繰り返すのか。
『三行で撃つ』近藤康太郎(CCCメディアハウス(現CEメディアハウス) 2020年)
佐藤友美さんは、今でも書くことに迷い、戸惑い、怖くなる、と書き綴ったあとに、太文字でひとこと、こう書いています。
それでもやっぱり、書いていく
『書く仕事がしたい』佐藤友美(CCCメディアハウス(CEメディアハウス) 2021年)
田中泰延さんは、書くことで世界は狭くなることについて、こう結んでいます。
しかし、恐れることはない。なぜなら、書くのはまず、自分のためだからだ。
『読みたいことを、書けばいい。』田中泰延(ダイヤモンド社 2019年)
(中略)
あなたは世界のどこかに、小さな穴を掘るように、小さな旗を立てるように、書けばいい。すると、誰かがいつか、そこを通る。
書くことは世界を狭くすることだ。しかし、その小さななにかが、あくまで結果として、あなたの世界を広くしてくれる。
僕の尊敬する書き手の動機には遠く及びませんが、僕なりに精一杯の宣言をしたいと思います。今なら、駅前のロータリーで叫ぶことだってできる!
一生、書き続ける。
一聴すると、安っぽく聞こえてしまうかもしれません。しかしこれこそが、映画『国宝』を観た僕に起きた、思考、行動の変容の全てです。
書くことが好きだ。
これからもずっと、ずっとずっと書き続ける。人生を楽しむために。
これは、僕が人生の後半戦に挑むための、所信表明です。
<参考文献>
- 『ピンポン』松本大洋(小学館)
- 『逆説の日本史⑤秀吉英雄伝』井沢元彦(小学館 2014年)
- 『日本史で読み解く「世襲」の流儀』河合敦(ビジネス社 2023年)
- 『歌舞伎の101演目解剖図鑑』辻和子(エクスナレッジ 2020年)
- 『三行で撃つ』近藤康太郎(CCCメディアハウス(現CEメディアハウス) 2020年)
- 『書く仕事がしたい』佐藤友美(CCCメディアハウス(現CEメディアハウス) 2021年)
- 『読みたいことを、書けばいい。』田中泰延(ダイヤモンド社 2019年)
本記事で紹介した映画

国宝
主演 吉沢亮
監督 李相日
「100年に1本の壮大な芸道映画」
——吉田修一(原作者)
画像引用元:Filmarks
※ 本ページはアフィリエイトプログラムによる収益を得ています
本記事で紹介した作品の原作

国宝(上・下巻)
吉田修一|朝日文庫
※ 本ページはアフィリエイトプログラムによる収益を得ています
※ 購入先リンクの飛び先はいずれも「上巻 青春篇」です
#宣伝会議田中泰延クラス 『国宝』week!
本記事は、2025年に宣伝会議で開催したライティング講座【「お金を払ってでも読みたいことを、自分で書けばいい」と思える書く力の教室】の最終課題「映画『国宝』のレビュー記事」を、「街角のクリエイティブ」掲載にあたって編集したものです。「#宣伝会議田中泰延クラス 『国宝』week!」と題して、これから8名の受講生の記事を1日1名ずつ順番に公開していきます。
▶︎ #宣伝会議田中泰延クラス 受講生による記事一覧はこちら
渡辺拓朗
映画
![]()
サウナ、カクテル、フジロック/書きたいものを書きたい時に書く「物書き」。人生のハーフタイムを終えて、これからは「やりたい事」を選ぶ側へ。書くことで、誰かの何かをそっと応援できたら。本業は某企業の研究所に勤めるサラリーマン。残る文章を、書きにいく。