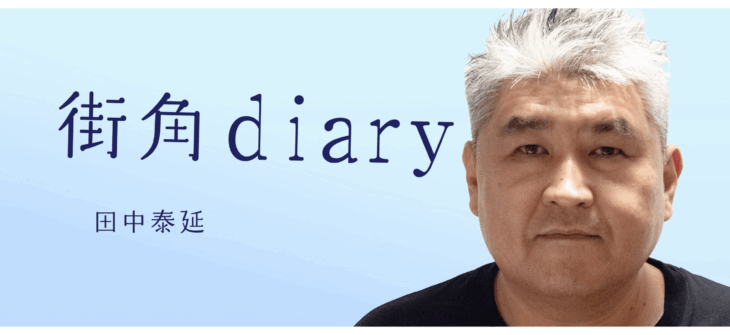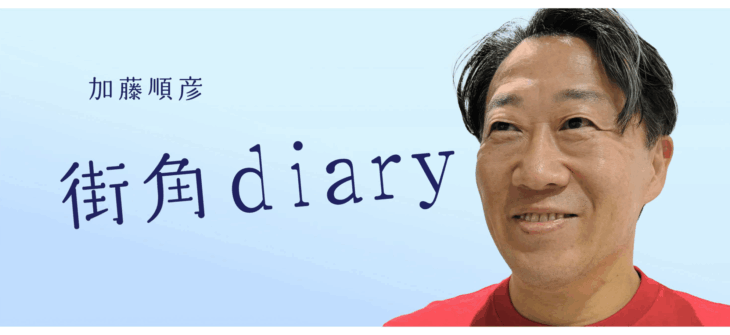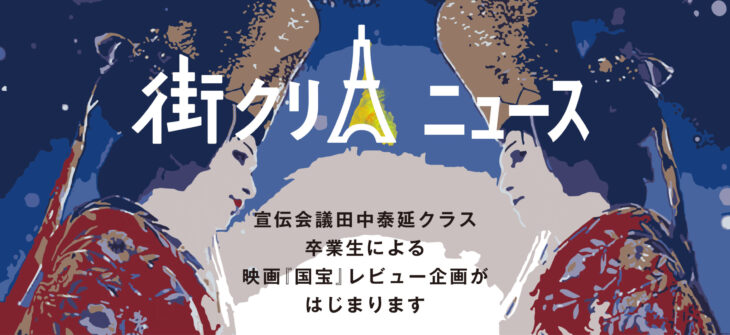仕事柄、海外に住む駐在員と現地で話をする。
彼らは自国を離れ、異国の地で長期間赴任する。
誰もがそこでの生活に容易に順応しているわけではない。
文化の違いに疲弊したり、孤独と向き合ったり、自国の家や家族、料理が恋しい夜もある。
海外留学であれば、帰国する日がある程度わかっているだろうが、駐在員には復路のチケットがいつ用意されるのか、わからないことの方が多い。
それが、精神的に重くのしかかることもあるという。
* * *
僕はあるとき、コペンハーゲンにいる取引先に、現地駐在の彼らが孤独とどう向き合っているのか訊ねたことがある。
「いつでも独り言を呟けるようになると、精神が安定するんですよ」
――その言葉が、印象に残っている。
それから数年が経ち、長期出張を重ねるうち、その意味の深さを少しずつ理解できるようになった。
僕は駐在員ほど長期間の滞在をしたことはないが、数か月の出張は何度か経験している。
初めての土地に足を踏み入れると、朝から晩まで流れてくる大量の「知らないこと」を浴び続けることになる。
英語圏であればどうにかなるが、それ以外の国では、レストランの入り口の判別すらままならず、「トイレ」の文字がわからなければ一大事である。
聞きなれない駅名やバス停、複雑に見える路線図。
ホテルやコンドミニアムのドアを開けば、見知らぬ景色と空気の匂い。
タクシーに乗っても、初めて見る街の風景が目の前を流れていく。
ビルに掲示された大型液晶モニターには、見たことのないシャンプーで長い髪を洗う美しいオネエサン。
郊外のレンガの壁には、しかめっ面でフォークを持つオジサンのポスター。
バスの運転手が早口で告げるアナウンスは、次の停留所すら聞き取れない。
こんな日々が数週間、数か月続くと、未知の刺激は楽しいとも思える一方、ボディブローのように少しずつ精神も削られていく。
独りで一言も話さない食事が増え、夜はベッドの上で身を小さくし、何とも言えない孤独に耐え、朝になるのを待つ。
日本にいるときにはないこの孤独の正体について、考えた。
僕の場合、それは「誰一人としてこの街で僕のことを知らない」という不安からだった。
街中で倒れたら、そのあとが怖い。
パスポートを片時も離さず持ち歩いてはいるわけでないので、どこの誰かも認識されず、身ぐるみ剝がされる可能性もゼロではない。
幸運にも誰かに助けられたとしても、自分の身体に何が起きているのか説明できないだろう。
旅をすれば、自国にいる時とは比較にならないほど五感は研ぎ澄まされ、脳は少しでも知らないことを咀嚼し、徐々に受け入れようとする。
ある夜、思わず小さく独り言を呟いた。
「次の駅はどこだろう」
「このバス、間違えてないよな」
――些細な言葉だった。
だが、口にすることで何かが少し和らぐのを感じた。
あの時の駐在員が言った「独り言」とは、こういうことなのかもしれない。
声に出すことで、自分の存在を確かめ、孤独の輪郭を少しずつ形作ることができる。
独り言は、未知を咀嚼するための小さな儀式でもある。
呟く言葉は意味のないもので構わない。
街が自分を受け入れてくれるのを待つのではなく、自分が街に馴染むための呪文のようなものだ。
独り言は心に、小さな秩序を作る。
孤独は完全には消えないが、心の軸を保つことができる。
駐在員の言葉は、旅や出張で味わう孤独を乗り越えるためのひとつの道標になったことを思い出し、ここに書き留めておく。
田所敦嗣さんの著書

スローシャッター
田所敦嗣|ひろのぶと株式会社
※ 本ページはアフィリエイトプログラムによる収益を得ています。
田所敦嗣
エッセイ
![]()
![]()
千葉県生まれ。水産系商社に勤務。エッセイスト。著書 『スローシャッター』(ひろのぶと株式会社)で、SNS本大賞「エッセイ部門」受賞(2023年)。フライ(釣り)、写真、野球とソフトボールが趣味。人前で声が通らないのがコンプレックス。

 更新日: 2025.12.25
更新日: 2025.12.25