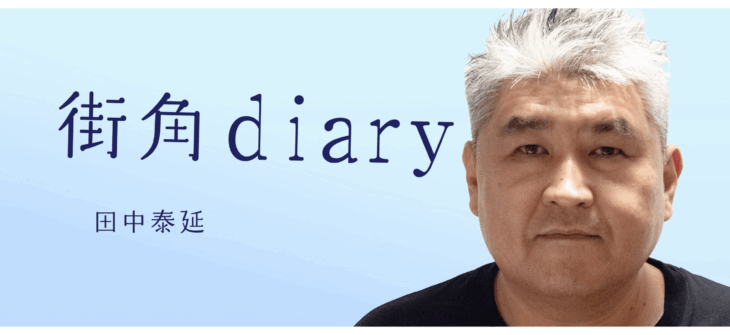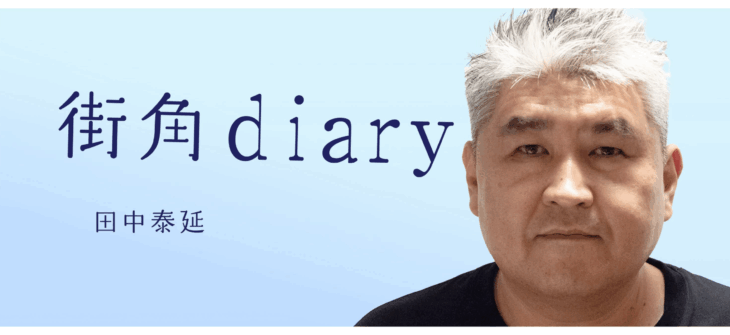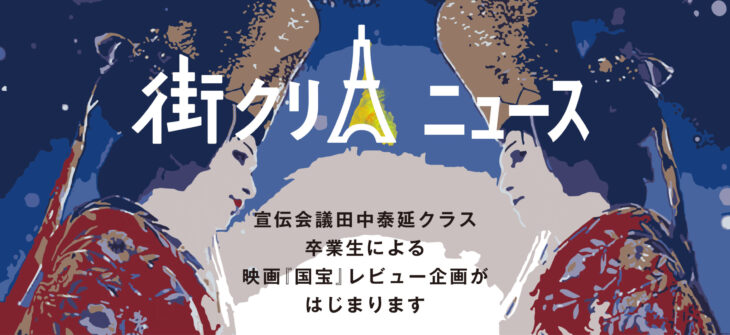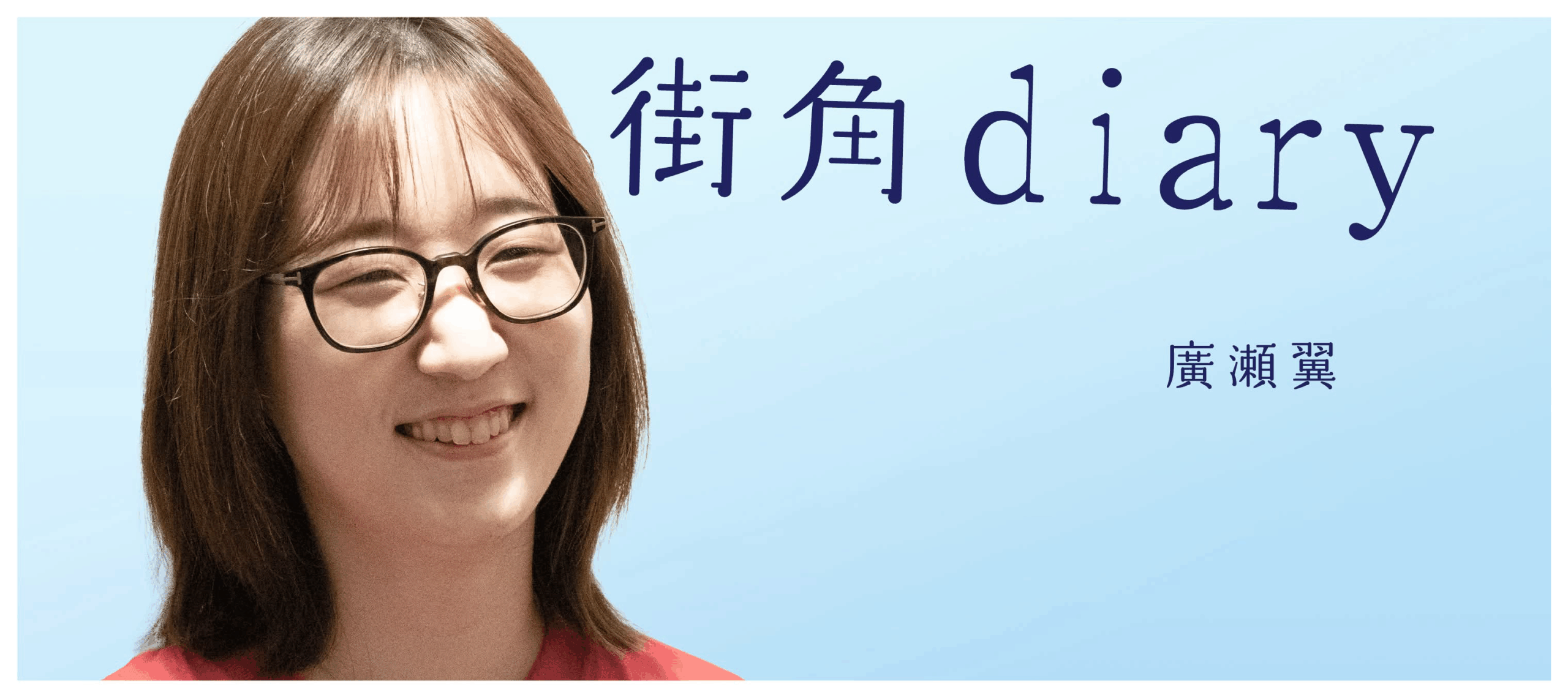
Hiroshimas
今年も、8月6日を迎えました。
この時期になると、毎年必ず読んでいた記事があります。
広島県の運営するWebメディア「国際平和拠点ひろしま」で2020年に公開された、田中泰延による記事『Hiroshimas』。
でも現在、「国際平和拠点ひろしま」のサイトは休止状態で、『Hiroshimas』も読めなくなっています。
理由は、昨2024年12月30日にサイトが不正アクセスを受けたこと。
* * *
それでも読みたかった私は、探しました。誰かがアーカイブを取っていないかと。
そうしたら、「Wayback Machine」で閲覧することができました。画像が一部表示されなくなっていますが、全部読めます。
そのリンクを、シェアします。
▶︎ 「Hiroshimas」田中泰延|日本語版 Wayback Machine
▶︎ 「Hiroshimas」田中泰延|英語版 Wayback Machine
* * *
広島県にも記事について問い合わせましたが、不正アクセスの犯人によって記事データ等が奪われてしまい、復旧には相当な時間がかかる様子。
そこで、県公式ホームページおよび「被曝・終戦80年特設サイト」で順次復旧・情報発信をしていくそうです。
でも、『Hiroshimas』が復旧の対象になっているのか、いつ復旧されるのかは、前回問い合わせた段階ではわかりませんでした。
まずは会員情報等の対応。そしてコンテンツ復旧は、どんな記事があったのか・何を復旧するのかのリスト整理からしていくというお話でした。
「この記事の復旧を望む声をいただいたことも踏まえて、今後の復旧リストも検討していきます」
窓口の女性はそうおっしゃってくださいましたが、再び広島県の管理するページで読めるようになるかは、まだわかりません。
* * *
1945年8月6日、日本時間午前8時15分。原子爆弾「リトルボーイ」投下。
それから、80年が経ちました。
NHKのニュースによると、被爆者が今年初めて10万人を下回ったといいます。
小学6年生の時に行った修学旅行は、広島での平和学習でした。原爆資料館、原爆ドーム、平和記念公園での外国人への英語インタビュー、そして「語り部」の方にお話を聞く時間。
その「語り部」も少なくなり、高齢化している今。どのように当時の様子や市民の思いを語り継いでいくのか——。
国際社会の緊張が高まる中、唯一の被爆国として、一つの大きな役目であり、改めて考えていきたいことです。
* * *
田中泰延の『Hiroshimas』は、その一つの解だと、私は思っています。
80年前、機関車の乗務員として糸崎と広島を毎日往復していたお父さんの話。
そのお父さんが、他の話はしてくれるのに、原爆の話は言葉を詰まらせて聞けなかったこと。
「この旅は、もう話せぬ父と私の対話になる。父がいったい、広島で何を見たかを見ようとする旅になるだろう。」
田中泰延『Hiroshimas』より
広島駅、広島城、広島平和記念資料館、そして原爆ドーム。
その一つひとつの景色を目の奥に焼き付けるように写真を撮り、学芸員の方に丁寧にお話を伺い、さまざまな資料に当たる田中泰延。
そうしてたどりついた、「恥」という感覚……。
人々に継がれていくのは、そして一人ひとりが考え思いを馳せられるのは、データではありません。「こんな取り組みをしています」という発表でもありません。
「人間」です。そして、「現在との接点」です。
人の声、人が実際に見たこと、そしてそれを通して何を感じたのか——。
それが綴られた田中泰延の『Hiroshimas』は、広島県のサイトにあってこそ意味がある。そう、思っています。
再び広島県のサイトで読める日が来ることを、願っています。
再び読めるようになるよう、私たちも働きかけていきます。
だけど今日は、どうぞWayback Machineでお読みいただけたら幸いです。
▶︎ 「Hiroshimas」田中泰延|日本語版 Wayback Machine
▶︎ 「Hiroshimas」田中泰延|英語版 Wayback Machine
廣瀬 翼
レポート / インタビュー
![]()
![]()
1992年生まれ、大阪出身。編集・ライター。学生時代にベトナムで日本語教師を経験。食物アレルギー対応旅行の運営を経て、編集・ライターとなる。『全部を賭けない恋がはじまれば』が初の書籍編集。以降、ひろのぶと株式会社の書籍編集を担当。好きな本は『西の魔女が死んだ』(梨木香歩・著、新潮文庫)、好きな映画は『日日是好日』『プラダを着た悪魔』。忘れられないステージはシルヴィ・ギエムの『ボレロ』。