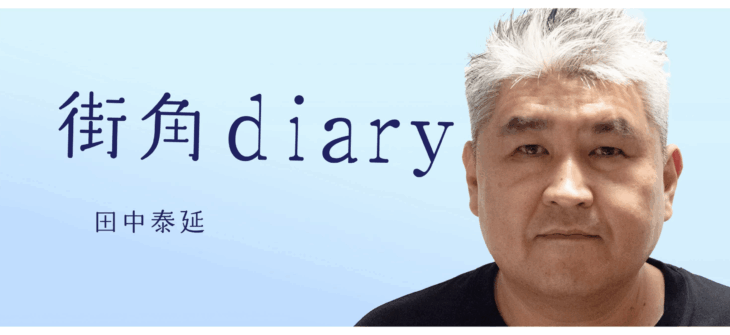1.映画『国宝』大ヒット
皆さんポップコーンはお好きですか?ポップコーンと言えば映画の友ですね。映画館で食べるポップコーンはなんであんなに美味しいのでしょうか。食べ始めると止まらなくなり、映画が始まってすぐに食べ終わってしまうこともめずらしくありません。が、しかし、そのポップコーンが全然減らない映画が出現したのです。目がスクリーンに釘付けになり、ポップコーンを食べることを忘れさせてしまう映画、それが『国宝』です。

2025年12月の段階で興行収入は180億を超え、『踊る大捜査線 THE MOVIE 2 レインボーブリッジを封鎖せよ!』の持つ記録を22年ぶりに塗り替え邦画実写歴代1位となり、2025年の邦画を代表する映画となりました。公開から6か月以上たった今でも上映は続いており、劇場を訪れる人の年代が幅広いことからも、人気の程がうかがえます。
『国宝』は吉田修一の同名小説を映画化したもので、任侠の一門に生まれながらも、歌舞伎役者の家に引き取られ、芸の道に人生を捧げた男の生涯を描いた一代記です。主人公である立花喜久雄を吉沢亮が演じ、歌舞伎の名門の御曹司である大垣俊介を横浜流星が演じています。歌舞伎を演じる才能を持つ喜久雄と歌舞伎の名門の血筋を持つ俊介が友情を育みながらも、お互いにないものを求めて葛藤する様や、それを取り巻く人々の人間模様が3時間にギュッと凝縮され、そこに歌舞伎の舞台シーンが加わり、見るものを片時も飽きさせない映画になっています。
ここでは、映画『国宝』の何がそこまで人々を惹きつけるのか、『国宝』製作までの歩みを中心に考えてみたいと思います。
2.歌舞伎の歴史
『国宝』は歌舞伎の世界を描いた映画です。まず、歌舞伎の歴史をおさらいしてみましょう。歌舞伎のルーツは、慶長8年(1603)に出雲阿国という女性が始めたとされる「阿国歌舞伎」からと言われています。この後「阿国歌舞伎」に端を発し、女性が演じる「女歌舞伎」が流行していきます。中でも遊女屋が経営する歌舞伎の座は遊女歌舞伎と呼ばれ、当時最先端の楽器だった三味線の演奏に、一度に5、60人の遊女が豪華な衣装で登場するという大掛かりな演出で、大変な人気を博したそうです。しかし、女性をめぐっての喧嘩などが絶えなかったため、寛永6年(1629)には「女歌舞伎」の禁令が出され次第に姿を消していったと言われています。「女歌舞伎」が禁止された後、美少年(稚児・若衆)による「若衆歌舞伎」が人気を集めます。「若衆歌舞伎」は能や狂言を当世風にアレンジしていたものを演じていたようです。女形の出現もこの頃と言われています。
その後、「若衆歌舞伎」も禁止され、若衆のシンボルである前髪を剃り落とし、額を剃り上げた野郎頭になることを条件に再開されることとなったのが、現在の歌舞伎に連なる「野郎歌舞伎」の始まりと言われています。若衆歌舞伎禁止後、役者たちが歌舞伎の再興を願い、「物真似狂言尽」と名称を改めることで上演を許可されました。また、この頃から芝居は決まった場所で行われるようになり、江戸では 猿若(中村)座、森田座、市村座、山村座の4座が、京都では四条河原、大坂では道頓堀にそれぞれ大きな芝居小屋が立ちました。そこで人気を博した役者が世襲により芸を伝承していったのが歌舞伎の家の始まりです。
劇中で立花喜久雄は「花井東一郎」という芸名で舞台に立ち、渡辺謙演じる「花井半二郎」や大垣俊介の「花井半弥」とともに「丹波屋」と呼ばれていました。「花井東一郎」「花井半二郎」「花井半弥」という名前は名跡(みょうせき)と呼ばれるものです。名跡は先祖代々受け継がれてきたもので、単なる芸名ではなく、特定の家が培ってきた芸風や伝統をも象徴するものです。名跡を継ぐことを「襲名(しゅうめい)」と呼び、襲名披露は歌舞伎界の大きなイベントです。代表的な名跡には「市川團十郎」「中村歌右衛門」「尾上菊五郎」などがあり、これらの名前は長い歴史の中で名声を得た俳優によって名乗られてきました。
一方「丹波屋」は「屋号(やごう)」と呼ばれ、役者の家系や一門を表す「看板」のようなものです。役者が登場した時や、見せ場で「〇〇屋」と客席から上がる掛け声も「屋号」です。上に挙げた名跡にはそれぞれ屋号があり、「市川團十郎」は「成田屋」、「中村歌右衛門」は「成駒屋」、「尾上菊五郎」は「音羽屋」と呼ばれています。
江戸時代から300年以上続く歌舞伎の世界、そこにはこれまでに培われた伝統と歴史の重みがあります。
3.小説『国宝』の挑戦
原作は吉田修一の小説『国宝』です。『国宝』は2017年1月1日から2018年5月29日まで新聞小説として朝日新聞に連載され、2018年9月に刊行されました。吉田修一の小説が新聞に連載されたのは『悪人』につづいて2作品目です。
『悪人』は九州の地方都市を舞台に、殺人事件を起こした土木作業員の清水祐一と、彼と共に逃避行に出た女性、馬込光代の物語です。事件にかかわる人々の行動から「いったい誰が本当の悪人なのか?」という深い問いを読者に投げかけます。『悪人』は吉田修一にとって初めての新聞小説であり、かつ、初の犯罪小説でもあり、彼自身にとって大きな挑戦だったのではないかと思われます。そして『悪人』も雪の日から話が始まるのです。
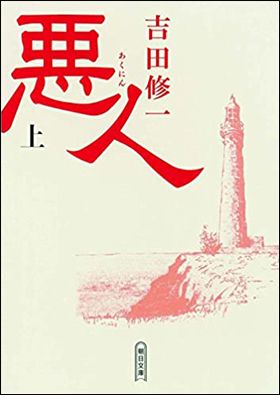
歌舞伎を題材とした小説としては宮尾登美子の『きのね』が有名です。「きのね」とは芝居の幕が始まる合図として打たれる拍子木の音のことです。『きのね』は歌舞伎の名門の家へ奉公に行った女性、光乃が、御曹司、雪雄と結婚し、おかみさんになるまでを描いた一代記です。この御曹司は十一代目市川團十郎がモデルと言われています。女性の目線から歌舞伎の世界の内側が生き生きと描かれています。作中の会話の端々から歌舞伎の家の伝統の重み、血の重みを感じることができます。

この他にも歌舞伎を題材とした小説はありますが、有名な歌舞伎役者の伝記的な作品が多い印象があります。歌舞伎役者を主人公に据えて、フィクションとして、その生涯を書ききった作品は多くはなく、その意味で吉田修一にとっても『国宝』の執筆は大きな挑戦だったと思われます。
『国宝』の執筆にあたり、四代目中村鴈治郎の黒衣となり、約3年間、歌舞伎の世界をその舞台裏から観察したそうです。ちなみに黒衣とは、全身黒い衣裳に身を包み、顔を隠して、小道具の受け渡しや衣裳の着替えなどを手伝い、舞台進行を裏方から支える人のことです。WEBサイト「好書好日」のインタビュー記事「吉田修一さん「国宝」インタビュー 歌舞伎の黒衣経験を血肉に、冒険し続けた4年間」の中で、歌舞伎の舞台そのものを描く苦労について、吉田修一はこう語っています。
作家としても、あそこで生まれて初めて歌舞伎の舞台というものを描写するわけですよ。そのプレッシャーたるや相当なもので、どうすれば歌舞伎っぽく見えるのかって本当に何度も描き直しをしました。
出典:吉田修一さん「国宝」インタビュー 歌舞伎の黒衣経験を血肉に、冒険し続けた4年間(好書好日)
そうした試行錯誤を経て、歌舞伎の世界を正面から描いた作品が生まれました。この挑戦について再びインタビューから引用します。
やっぱり、自分にとってはターニングポイントになった『悪人』という連載をした同じ媒体で十年ぶりに書かせてもらえるというので、この十年、自分がどれくらい作家として成長したのか、試してみたいというのがありました。その前に描いたいくつかの作品が、映像化されたりもして、自分なりにちょっとだけ自信になっていたので、極端な話、ここで大失敗してもいいかぐらいの感じですよ。本当にもう、博打というか、作家人生賭けてやるくらいのことをやりたくなったんです。
出典:吉田修一さん「国宝」インタビュー 歌舞伎の黒衣経験を血肉に、冒険し続けた4年間(好書好日)
こう語るほどの挑戦があってこそ、『国宝』は世に生まれたと言えましょう。
4.李相日監督の歩み
『国宝』の監督は李相日です。これまでの単独の監督作品として『青~chong~』『BORDER LINE』『69 sixty nine』『スクラップ・ヘブン』『フラガール』『悪人』『許されざる者』『怒り』『流浪の月』が挙げられます。このうち『悪人』『怒り』は『国宝』とともに吉田修一の原作です。ここでは『フラガール』以降の作品について見ていきましょう。
『フラガール』は炭鉱に替わる町おこしとして立ち上げた、常磐ハワイアンセンター誕生の実話を映画化した作品で2006年に公開されました。フラダンスを教えるために東京からやってきたダンサーと炭鉱の娘たちとの絆を描きます。東京からやってきたダンサーを松雪泰子、炭鉱町の娘の1人を蒼井優、その兄を豊川悦司が演じました。この映画の最後にフラダンスをステージで踊る場面があるのですが、踊りを見せるという点で『国宝』との共通点が見出せます。アップと引きの映像がテンポよく切り替わり、ダンサーの背後から客席を映すショットなど、『国宝』の歌舞伎の舞踊シーンの原点をみることができます。また、美術は『国宝』の美術でもある種田陽平が2004年公開の『69 sixty nine』に続いて担当しました。音響の白取貢と編集の今井剛は『国宝』まで李相日監督と歩みをともにします。炭鉱の娘たちが紆余曲折を経てフラガールを目指す姿が感動を呼ぶ、いい映画です。

『悪人』は前述の小説を映画化した作品で2010年に劇場公開されました。土木作業員の清水祐一を妻夫木聡、彼と共に逃避行に出る女性、馬込光代を深津絵里が演じました。二人はその年の日本アカデミー賞において、妻夫木聡は最優秀主演男優賞、深津絵里が最優秀主演女優賞をそれぞれ受賞し、映画自体も高い評価を受けました。罪を犯した男性とその男性を慕う女性の逃避行は、『国宝』に登場する、「曾根崎心中」と話の構造がそっくりです。『悪人』で、セリフに頼るのではなく、その仕草や表情だけでその人物の感情が伝わってくるような演出が確立されたように見えます。灯台の屋上で、夕陽を受けて、祐一が海を見つめるラストシーンが印象に残っていますが、『国宝』の喜久雄が旅回り先のホテルの屋上で人ならざるもののように踊るシーンとつながっているように感じました。衣装デザインは小川久美子が本作から『国宝』まで担当します。妻夫木聡、深津絵里、満島ひかり、岡田将生、樹木希林、柄本明といった演技モンスターが激突、悪人とは何なのかを観客に突きつける、いい映画です。
『許されざる者』は1992年に公開されたクリント・イーストウッド監督・主演による西部劇映画『許されざる者』のリメイクで、2013年に公開されました。明治時代初期の北海道を舞台に、江戸幕府側の残党・釜田十兵衛が再び賞金稼ぎとして戦いに身を投じるさまを描いた作品です。釜田十兵衛を渡辺謙が演じ、脇を柄本明、佐藤浩市らが固めます。まず、渡辺謙の起用が『国宝』へと繋がっています。また、過去の時代を撮影するという点でも『国宝』との関連を見出すこともできます。そして、クライマックスの壮絶な殺陣シーンは『国宝』冒頭のヤクザの抗争によって喜久雄の父親が命を落とすシーンとつながって見えます。『国宝』関連のキャストとして、渡辺謙とともに、三浦貴大、芹澤興人の名前を見つけることができます。十兵衛が抑えて、抑えて、最後に爆発、いい映画です。

『怒り』は『悪人』に続き、吉田修一の同名小説を原作とし、2016年に公開されました。殺人事件の犯人に似た特徴をもつ三人の男をめぐる、群像ミステリードラマです。主演は『許されざる者』に続いて渡辺謙、三人の男を森山未來、松山ケンイチ、綾野剛が演じ、広瀬すず、宮崎あおい、妻夫木聡らが共演しています。『国宝』関連のキャストとして前作に続き、渡辺謙、三浦貴大、そして高畑充希が出演しています。沖縄、東京、千葉を舞台とした話がそれぞれ独立して進むのですが、それぞれの舞台が切り替わる時に、音だけが前の場面から残っていたり、次の場面の音だけが先に映像にかぶったりする演出が多用されます。『国宝』でも、場面の切り替わりに同様の演出を使うことで、観客の集中が途切れない効果あったように感じました。照明は本作から『国宝』まで中村裕樹が担当します。三人の男に森山未來、松山ケンイチ、綾野剛をキャスティングした時点で勝負あり、終わりまで目が離せない、いい映画です。

『流浪の月』は2022年に凪良ゆうの同名小説を映画化したものです。9歳のときに誘拐事件の被害者となり、広く世間に名前を知られることになった女性、家内更紗と、その事件の加害者とされた当時19歳の大学生・佐伯文が15年後に再会を果たす様が描かれています。家内更紗を広瀬すず、佐伯文を松坂桃李、広瀬すずの恋人役を横浜流星が演じました。『国宝』つながりでは、横浜流星の起用が挙げられます。横浜流星はモラハラ気質のある恋人役を演じています。ちょっとした表情や仕草から、内に持つ弱さをうかがい知れる演技が印象的でした。また、白鳥玉季が更紗の少女時代を好演していることも、『国宝』で喜久雄の少年時代を演じた黒川想矢の好演と重なります。少女、少年の演出についてこの時の経験が国宝にも生かされたのではないかと想像します。撮影監督には、ポン・ジュノの元で『パラサイト 半地下の家族』を撮ったホン・ギョンピョを起用しました。『国宝』でも海外から撮影監督としてソフィアン・エル・ファニを呼んでいますが、『流浪の月』での成功体験がその起用を後押ししたのではないでしょうか。音楽は『国宝』でも音楽を担当した原摩利彦が手掛けています。文と更紗の二人だけの儚い世界が淡い光とともに映し出され、映像作品ならではの表現を味わえる、いい映画です。

5.吉沢亮の歩み
『国宝』の主演は言わずと知れた吉沢亮です。彼なくしてはこの映画は成立しなかったのではないでしょうか。彼の『国宝』につながる歩みを見ていきましょう。まずは出世作となった『仮面ライダーフォーゼ』です。『仮面ライダーフォーゼ』は2011年9月4日から2012年8月26日まで、テレビ朝日系列で全48話が放映された、東映製作の特撮テレビドラマ作品です。朔田流星、仮面ライダーメテオとして第17話から出演し、親友を救うため、潜入員として素性を隠して仮面ライダーに近づくといった、二面性をもつキャラクターを好演しています。また、その親友役として、横浜流星も出演しており、第32話では二人の熱い友情シーンが見られます。『仮面ライダーフォーゼ』での共演を通じて、『国宝』でも見られる二人のブラザーフッドは既に築かれていたと言えましょう。

『仮面ライダーフォーゼ』での活躍をきっかけに多くのテレビドラマや映画に出演しますが、『国宝』との関連で注目されるのが、『キングダム』シリーズへの出演です。『キングダム』は原泰久の同名漫画を映画化した作品で、古代中国の春秋戦国時代を舞台に、中華統一を目指す後の始皇帝・第31代秦王・嬴政(えいせい)と、その元で天下の大将軍を目指す主人公、信の活躍を中心に描かれています。シリーズ第1作目『キングダム』は2019年に公開されました。監督は佐藤信介、主人公、信を山﨑賢人が演じ、吉沢亮は嬴政を演じました。ここで吉沢亮は、心優しき一人の青年が、その立場ゆえ、徐々に皇帝としてのオーラを纏って行く様を好演しています。一歩ずつ皇帝へと歩む道のりが、人間国宝への道のりと重なります。熱い友情と迫力のアクション、かっこいい長澤まさみが見られる、いい映画です。

ちなみにXで「始皇帝」と検索したら上位にはこんなツイートが並んでいました。
始皇帝の声が聞けるのは「ひろのぶと通信」だけ!始皇帝に励ましのおたよりを書こう!
— 田中泰延 (@hironobutnk) October 14, 2025
ひろのぶと通信 10月10日発行号|ひろのぶと株式会社 @hironobutoco https://t.co/i9IeiKmiZG
大スクリーンに地球始皇帝、という場に今日は居ます。 pic.twitter.com/diOmNaE2Ga
— 加納穂乃香、ひろのぶと株式会社 (@kmpsh_hnk) February 17, 2023
私も始皇帝に励ましのおたよりを書いてみたいと思います。
呉美保監督の2024年に公開された映画『ぼくが生きてる、ふたつの世界』も印象に残っています。作家でエッセイストの五十嵐大による自伝的エッセイ「ろうの両親から生まれたぼくが聴こえる世界と聴こえない世界を行き来して考えた30のこと」を映画化したものです。吉沢亮は主人公、大を演じています。この映画で、彼はろうの両親を持つ子として、かわいそうな子として見られることへのいらだちや、東京へ出て自分の生き方を模索していく様子を見事に演じていました。親に対して素直になれないところや、若者がもつ気怠さや生意気さを表情一つで表現して見せるなど、吉沢亮の魅力が十分引き出された作品と言えるでしょう。作品中に大が劇団のオーディションを受けて落ちる場面があり、その理由が「死んだ目をしている」だったのですが、吉沢亮の「死んだ目」が大好きな私としては、思わず笑ってしまいました。なにげない日常のエピソードの積み重ねですが、しっかりドラマになっていて、最後は見ている方が泣かされるという、いい映画です。

ろう者・難聴者の親を持つ聞こえる子供のことを、Children of Deaf Adultsの頭文字から「コーダ」と呼ばれますが、2022年に公開されたシアン・ヘダー監督による『Coda コーダ あいのうた』も同じテーマを扱った作品です。劇中で流れる曲はどれも気分が上がる曲ばかり、家族の絆に胸が熱くなる、いい映画です。

6.「家」と「血」の映画の系譜
ここからは『国宝』とのつながりが感じられる映画を見ていきましょう。
『残菊物語』は溝口健二監督による、歌舞伎の御曹司と使用人である女性との恋愛を描いた作品で1939年に公開されました。本作は、実在の人物、二代目尾上菊之助が主人公で、花柳章太郎が演じました。花柳章太郎は演劇の女形役者として知られ、後に人間国宝となりました。

菊之助は名家の御曹司というだけで周りからはちやほやされる中、甥っ子の乳母であるお徳から演技について厳しい言葉を投げかけられます。それに感銘を受けた菊之助はお徳に心を寄せます。しかし、身分違いということでお徳は家に返されます。そのことがきっかけとなり菊之助は家を出て、その後お徳と一緒になり、旅回りの一座に身を落とします。旅回りで培った菊之助の芸が認められ、家への復帰が認められますが、その際、お徳は自ら身を引きます。歌舞伎の家の御曹司が家を出て、旅回りで芸を磨いて、一線に復活するといった話の構造が『国宝』の下敷きになっているようです。映像表現の面でも、楽屋から舞台へ役者が出ていく姿をカメラが追いかけてワンカットで撮影されていたりする所に共通点を見出せます。旅回りに身を落とした菊之助が見事に復活する演目が「積恋雪関扉」です。この演目は『国宝』の冒頭、長崎の新年会のシーンで喜久雄と徳治が演じた演目でもあり、ここもつながっているようです。最後の場面では、菊之助の船乗り込みの姿と病の床に伏せるお徳の姿が交互に写し出され、花形役者に返り咲いた菊之助の晴れやかな姿と、献身によって菊之助を支えながらも死にゆくお徳の対比が、見ているものに強い印象を残します。そして、このシーンに、『国宝』の最後、劇場に向かう喜久雄とカメラマンとなった娘、綾乃の姿が交互に写し出されるシーンが重なります。カメラのアングルが完璧、お徳の献身に涙、いい映画です。
ちなみに、船乗り込みは道頓堀で今でも行われており、下の写真は四代目中村鴈治郎襲名披露の時のものです。

『国宝』は「家」と「血」の映画でもあります。そこで思い浮かぶのがフランシス・フォード・コッポラ監督の1972年に公開された傑作映画『ゴッドファーザー』です。年代記であること、上映時間が3時間近くあること、ファミリーの話であること、陰影のある重厚な映像などが『国宝』に連なっているようです。前半で登場人物のキャラクターを描き、後半は一気にストーリーが展開して行く構成で、長時間でも観客を飽きさせない作りも引き継がれているようです。また三男のマイケルが父の死をきっかけとして、まるで悪魔に魂を売り渡したかのように冷酷に一族の長に君臨する様は、喜久雄が悪魔と契約して人間国宝への道を歩む姿とも重なります。今更この映画についての説明は不要でしょう、大傑作。
『国宝』では俊介、喜久雄とも旅回りすることで役者として成長するという筋立てになっていますが、旅回りの芸人ということで思い出されるのが、1954年に公開されたフェデリコ・フェリーニ監督の『道』です。旅芸人のザンパノと彼に二束三文で買い取られた女性、ジェルソミーナの物語です。ザンパノとジェルソミーナがオート三輪で旅回りする姿と、喜久雄と彰子が車で旅回りする姿が重なります。彰子の車がFIATでイタリア製だったのは偶然でしょうか。ザンパノが、気がふれたようになってしまったジェルソミーナを置き去りにする場面も、喜久雄が何かに取り憑かれたように踊るのを見て、彼のもとを去る彰子につながります。ニーノ・ロータの美しい音楽、見れば自分の歩んできた道に思いを馳せざるをえない、いい映画です。

7.『国宝』の魅力
ここからは、『国宝』で印象に残った点について語りたいと思います。
まずは、劇中で取り上げられた歌舞伎の演目についてです。喜久雄が歌舞伎俳優となってから演じた演目は「藤娘」「二人道成寺」「曾根崎心中」「鷺娘」ですが、「曾根崎心中」を除いて、すべて舞踊の演目です。舞踊のシーンを映画ならではのカメラワークでテンポよく見せることで、歌舞伎になじみのない観客でも十分楽しめるものとなり、歌舞伎の舞台を作品の中心に据えることが可能になりました。前述の『フラガール』での経験が生かされていたのではないかと思います。
「曾根崎心中」は劇中で唯一、江戸時代の町人たちの日常的な出来事や風俗を題材にした世話物の演目です。「曾根崎心中」のストーリーを、俊介の命を懸けた演技という、映画自体のストーリーとも重ね合わせることで「曾根崎心中」を演じているシーン自体が物語の山場と重なり、見るものに大きな感動を与えていました。
劇中でひときわ存在感を放っていたのが、田中泯演じる小野寺万菊です。田中泯はダンサーとして活躍する一方、近年は多くの映画やドラマにも出演し、個性的な演技を披露しています。2023年に公開されたヴィム・ヴェンダース監督の『PERFECT DAYS』で踊るホームレスの姿が印象に残っています。

小野寺万菊は人間国宝として喜久雄を導く存在として位置づけることができます。浮世離れした師匠という意味では1984年に公開されたジョン・G・アヴィルドセン監督『ベスト・キッド』のミスター・ミヤギを思い出します。
「ほんと、きれいなお顔だこと。」から始まる万菊の言葉は強く印象に残ります。劇中の節目節目で発せられる万菊の言葉は、どれもその先の喜久雄の進む道を予見しているかのようです。
三浦貴大演じる竹野は歌舞伎の世界を外から眺める存在として重要な位置を占めます。観客の気持ちを代弁する役割ですね。最初は傍観者の立場でしたが、次第に喜久雄の魅力に惹かれていきます。このキャラクターに、2020年に公開された西川美和監督の『すばらしき世界』で、役所広司演じる元殺人犯を取材する、仲野太賀演じるTVディレクターが重なります。有名俳優を父に持つところも共通点ですね。

夕陽の屋上で喜久雄が踊るシーンは最も印象に残っているシーンの一つです。白塗りが剝がれた顔で踊る姿は人間離れしていて、黄昏の幻想的な光と相まって、喜久雄が遠いところへ行ってしまうように見えました。このシーンにトッド・フィリップス監督の2019年に公開された映画『ジョーカー』の劇中、階段でジョーカーが踊るシーンを重ねた人も多いと思います。

ただ、ここまで李相日監督の作品を見てきた後では、『悪人』の最後の灯台の屋上のシーンや、『流浪の月』の最後に更紗が文の喫茶店を訪れるシーンがより強く結びついているように感じます。
8.『国宝』が見せてくれたもの
ここまで、映画『国宝』に至る道のりを李相日監督の歩みとともに振り返り、過去作との比較でその魅力について考えてきました。歌舞伎という300年以上の歴史を持つ伝統芸能に、監督をはじめ、原作者の吉田修一、主演の吉沢亮をはじめ、横浜流星、渡辺謙らが正面からぶつかり、見事に描き切ったことに最も心が動かされました。歌舞伎を演じる場面を減らし、舞台裏での人間ドラマを中心に描くやり方や、歌舞伎の場面で代役を立てるという選択肢もあったはずですが、敢えてそれをやらず、役者本人が歌舞伎を習得し、それを物語の中心に据えるという、一番険しい道を選択しました。そのため、吉沢亮と横浜流星は撮影に入るまで1年以上かけて稽古したと言われています。
この覚悟について、歌舞伎役者である市川團十郎も自身のYouTubeで『国宝』について「本当に歌舞伎と向き合ったんだな」という感想を述べています。現代を代表する歌舞伎役者の目にもそのように映ったということから、彼らの本気度が伝わってきます。
目の前に大きな壁が立ちはだかった時、私はこれまで、その壁をないものとして見えないふりをしたり、壁を迂回して進むことを選びがちでした。そのような選択をしたことを後から悔やむこともありました。今回『国宝』の記事を執筆する中で、李相日監督をはじめとしたスタッフ、キャストが困難な課題に正面からぶつかり、それを乗り越え行く姿から、困難に立ち向かう勇気を分けてもらったような気がします。
『国宝』が多くのスタッフ、キャストでそれを成し遂げたように、必ずしも一人で困難を乗り越えて行く必要はないのです。一人の力で乗り越えられなければ、仲間を募り、仲間と力をあわせて乗り越えればいいのです。ただ、その信頼関係は積み重ねられた仕事によって培われていくこともここまでの歩みが示しています。
『国宝』が私に見せてくれたものは、血筋や家といった大きな壁に、たった一人でぶつかり、すべてを捧げることでその壁を乗り越えて、人間国宝にまで上り詰めた喜久雄の姿と、歌舞伎という長い歴史を持つ伝統芸能に正面からぶつかり、見事にそれを描き切った製作陣の姿でした。
最後は映画評論家、水野晴郎の言葉で締めくくりたいと思います。
「いやぁ、映画って本当にいいもんですね。」
本記事で紹介した映画

国宝
主演 吉沢亮
監督 李相日
「100年に1本の壮大な芸道映画」
——吉田修一(原作者)
画像引用元:Filmarks
※ 本ページはアフィリエイトプログラムによる収益を得ています
本記事で紹介した作品の原作

国宝(上・下巻)
吉田修一|朝日文庫
※ 本ページはアフィリエイトプログラムによる収益を得ています
※ 購入先リンクの飛び先はいずれも「上巻 青春篇」です
#宣伝会議田中泰延クラス 『国宝』week!
本記事は、2025年に宣伝会議で開催したライティング講座【「お金を払ってでも読みたいことを、自分で書けばいい」と思える書く力の教室】の最終課題「映画『国宝』のレビュー記事」を、「街角のクリエイティブ」掲載にあたって編集したものです。「#宣伝会議田中泰延クラス 『国宝』week!」と題して、これから8名の受講生の記事を1日1名ずつ順番に公開していきます。
三上 和彦
映画
![]()
1965年島根生まれ。フリーランスのプログラマー。料理をしていると落ち着きます。

 更新日: 2026.01.26
更新日: 2026.01.26