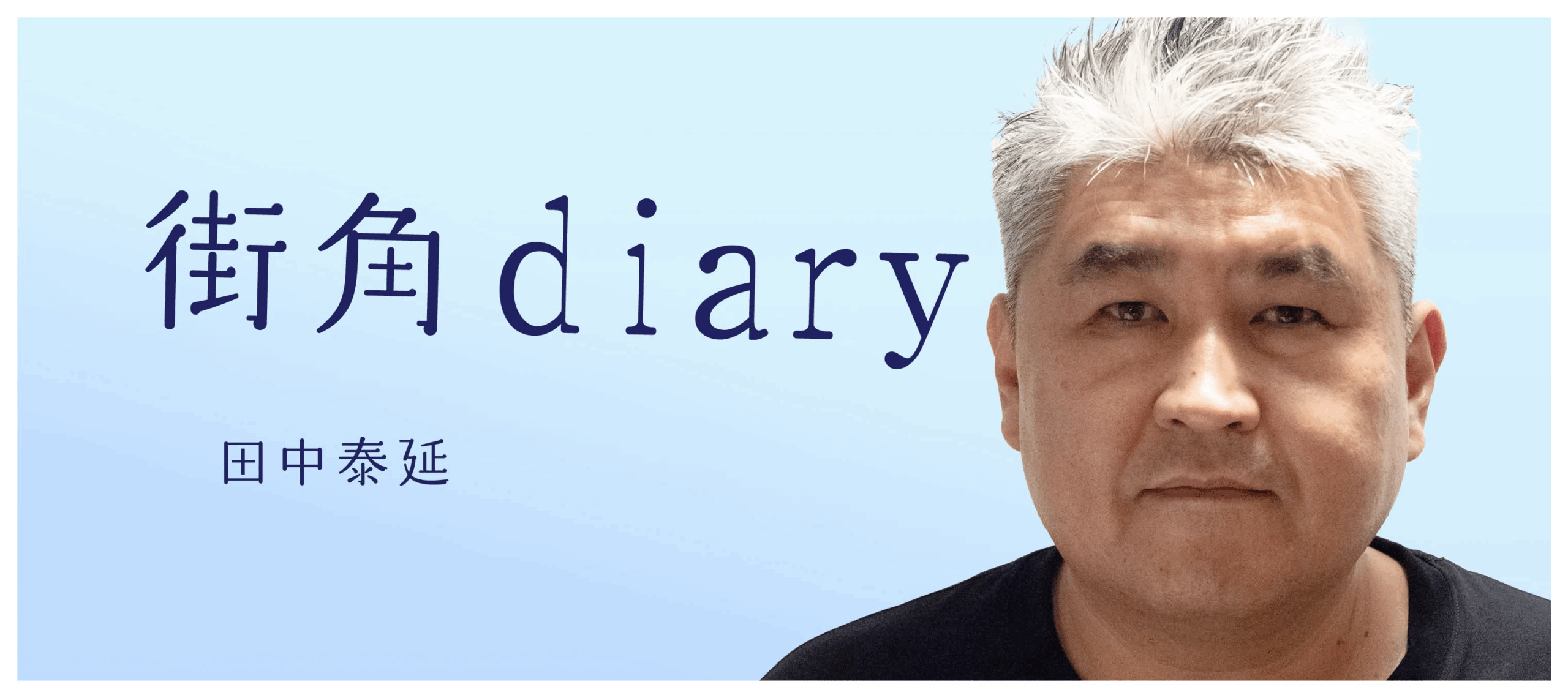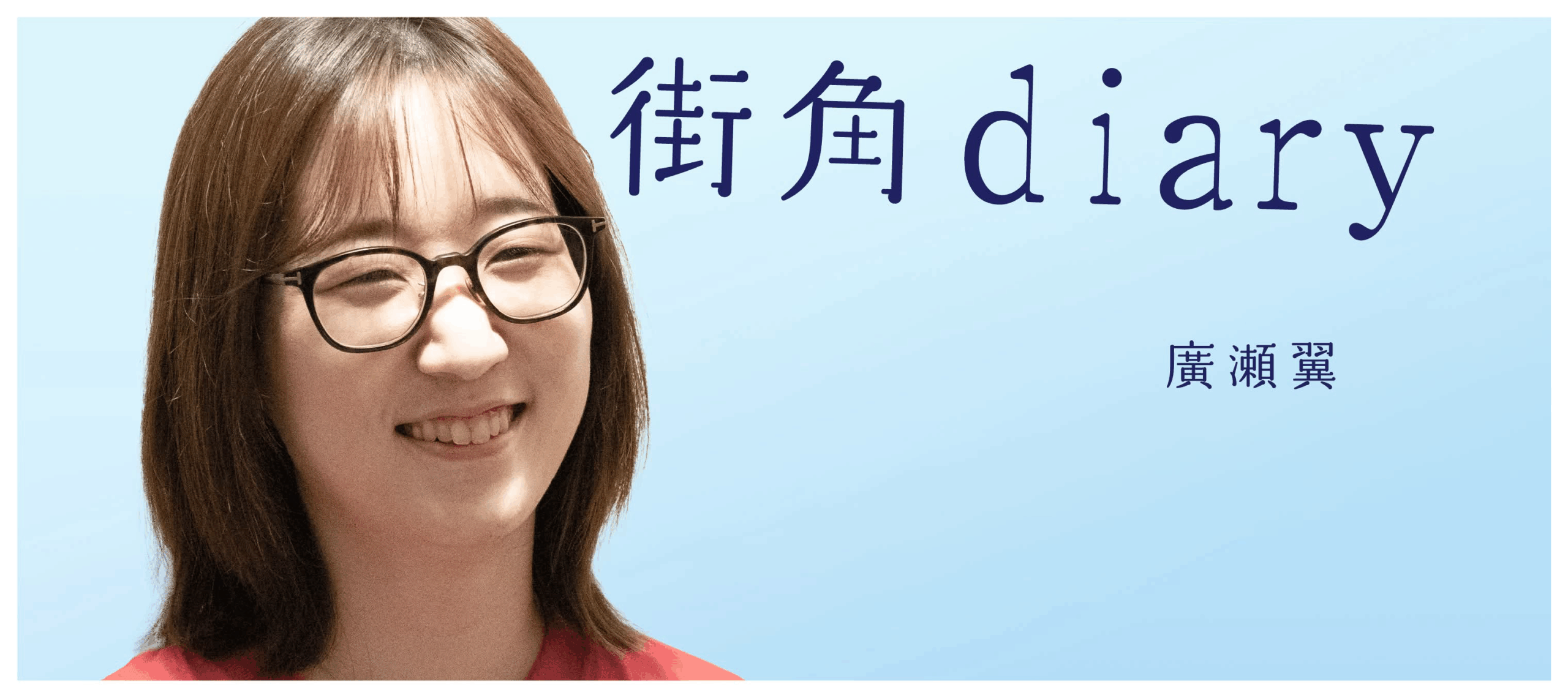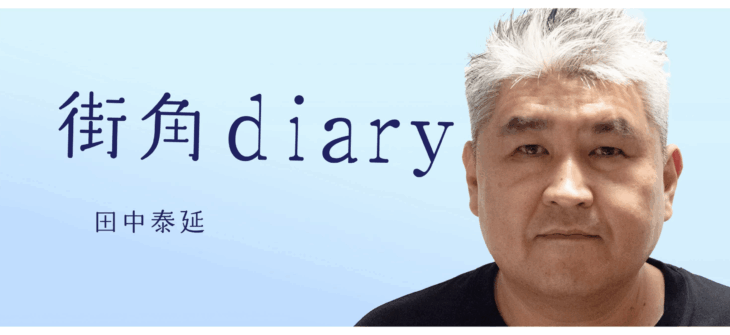2025年6月6日に公開された『国宝』(李相日監督)が、異例のロングランヒットを続けています。公開172日間で興行収入は173億を超え、『踊る大捜査線 THE MOVIE 2 レインボーブリッジを封鎖せよ!』(2003年公開/本広克行監督)が22年間守った173億5000万円の実写日本映画興収記録を、22年ぶりに塗り替え歴代1位となりました。
また、第98回米国アカデミー賞国際長編映画賞の日本代表作品にも選出され、日本文学振興会が『国宝』製作チームに第73回菊池寛賞を授与すると発表し、その勢いは衰えることを知りません。
さらには、「現代用語の基礎知識選 2025T&D保険グループ新語・流行語大賞」のトップテンに「国宝(観た)」がノミネートされるなど、『国宝』を評価するニュースはこれからも続々と届くと予想されます。
『国宝』観た勢としては、「国宝観た?」って聞きたくなる気持ちめちゃくちゃわかります。当時、「田中泰延の『お金を払ってでも読みたいことを、自分で書けばいい。』と思える書く力の教室」メンバーのなかで『国宝』を観ていないのが10人中2人だけで、私は観ていない側の1人だったのに、観た途端「ねぇ!国宝観た!?どこがよかった!?どっち好き!?喜久雄!?俊ぼん!?」と目を輝かせて人に聞いていました。それほど「凄いもん観た!人もこれを観たのか!?何を思ったのか!?知りたい!!」と大興奮するのがこの映画なのです。
もうひとつ『国宝』の凄さは、公開以降急激に伸びた興行成績はもちろんのこと、リピーターが続出している点だと思います。私も、2回観ました。この課題のためしっかり観ておきたいという気持ちもありましたが、「1回目に感じた気持ちをまた味わいたい!」と思ったからこそ、お金を払ってでも、3時間を確保してでも観に行きました。
そうそう、この映画、上映時間が3時間あります。もうご存じの方も多いと思いますが、なかなか長いですよね。しかも、休憩なしです。これだけ長いとトイレ問題が気になり、「鑑賞に踏み切れない」という人もきっと多くいらっしゃいますよね。
なぜ人々は3時間もある大作を繰り返し観たくなるのか。この感覚、スポーツ観戦に近いのではないかと思います。スポーツの試合も長時間に及び、途中のトイレ問題が頭をよぎることもあります。応援しているチームが点を取りそうな場面でトイレに行きたくなるかもしれない。それでも現地まで足を運ぶのは、自分の目でプレーを目撃し、選手と共にその試合で燃え尽きる感覚を味わいたいからですよね。
『国宝』もそんな臨場感があり、感情移入できる場面がいくつもあります。主人公・喜久雄の成長、ライバルである俊介の挫折からの成長、どちらが『国宝』と呼ばれる歌舞伎役者になるのか。観客席から手に汗握りながら、見守っている感覚になります。まるで贔屓の選手を応援するように、彼らの人生の一進一退に一喜一憂してしまうのです。そして、物語が最終盤に差しかかると、観ている自分自身も喜久雄と一緒に燃え尽きていく。スポーツの名勝負を観終えた後の放心状態、清々しいのに興奮しているようなあの独特の余韻が、エンドロールを見つめながら感じられます。
ちなみにトイレ問題ですが、私は映画館でドリンクを頼まないことで対策しました。特につらいと感じなかったのでご参考までに。巷では「ボンタン飴」を食べると尿意が止まるという噂があり、実践している人もいるようです。一説によると、主原料である水あめの元であるもち米に含まれているデンプンを摂取すると、血糖値と血液の浸透圧が高まって、体内の水分が尿として排出されにくくなる可能性があるようです。
私は食べ物を食べたら途端にトイレの存在が気になるタイプなので実践しませんでしたが、いずれにせよ物語がスタートしたら誰しも見入ってしまうのでそこまでトイレ問題は気にせずぜひ気軽に観に行ってほしいと思っています。
では、なぜ『国宝』は、これほどまでに人を魅了する物語なのでしょうか。『国宝』の監督である李相日監督は、なぜこのような深い人間ドラマを描き出すことができるのか。その秘密を探るために、まず李相日監督の手腕から見ていきたいと思います。
李相日監督の『悪人』(2010年公開)『怒り』(2016年公開)、そして『国宝』はいずれも長編映画で、複数の視点から人間ドラマを描き出す特徴を持っています。
李相日監督の『悪人』『怒り』、そして『国宝』はいずれも長編映画


映画『国宝』は、吉田修一の同名長編小説『国宝』を映画化した作品です。吉田修一が原作を担当し、李相日によって映画化されるのは『悪人』『怒り』に次いで今回で3作目となります。
それぞれの上映時間は『悪人』が139分(2時間19分)、『怒り』が142分(2時間22分)、『国宝』は175分(2時間55分)といずれも長時間に及んでいます。どの作品も登場人物が多いなかで、それぞれの人間ドラマが複雑に絡み合い、クライマックスまでの展開を長時間で描くというのは、李相日の得意技と言えるでしょう。
その秘訣の一つが、複数の物語を同時進行させる編集技術にあります。『怒り』では東京、千葉、沖縄での3つの物語が展開しますが、この3つの物語が時に交差する場面を効果的に挿入することで、観客の関心を途切れさせません。
この手法は『国宝』にも引き継がれています。異なる物語がクロスする構成によって、観客は場面の切り替わりに自然と注目し、長時間でも退屈することなく観ていられる。時には「このシーンとあのシーンは関係があるのかな?」と今後の展開を考察する楽しみも生まれます。1度ですべての仕掛けには気づけないので、何度も確認したくなる。これがリピーター増加の一因になっているのではないでしょうか。
私が好きなシーンは、俊介が一歩一歩足踏みしながら「う、ら、め、し、や」と言いながら前進していく場面です。「ここからはきっと俊介の話だ!」「俊介のターン、キターーーーーー!」と、物語も中盤に差しかかったところで期待感とともにグッと集中力が高まり、後半も引き込まれていきました。
物語は主人公・喜久雄の15歳から50歳までが綴られている

『国宝』は、任侠の一門に生まれながら歌舞伎の女形の才能があり、歌舞伎役者の元に引き取られた吉沢亮演じる立花喜久雄と、歌舞伎の名家に生まれ、幼いころから稽古を積み、跡取り御曹司として育てられた横浜流星演じる大垣俊介の相反する出自と才能の対比を描いた物語です。物語の軸として、喜久雄の15歳から50歳までが綴られています。
『悪人』『怒り』と長時間映画を製作した李相日ですが、今回喜久雄の一生を3時間内で納めるための構成とストーリー展開は、今年6月に開催された「上海国際映画祭」で李相日監督自ら、1993年のカンヌ国際映画祭パルムドール受賞作、チェン・カイコー監督の『さらば、わが愛/覇王別姫』をヒントにしたと発言しています。
『国宝』と『さらば、わが愛/覇王別姫』はともに京劇と歌舞伎という伝統芸能を舞台に、芸の道へ進む二人の若者の激動の人生を描いています。『さらば、わが愛/覇王別姫』を観てみると、ストーリー展開や時間経過がテンポよく進む場面があり、『国宝』も同じ印象を受けますので、気になった方は『国宝の番外編』として観てみるのもおすすめです。
さらに『国宝』の魅力を分解していくと、ライバルと切磋琢磨して頂点を目指すストーリー展開が、美内すずえの漫画『ガラスの仮面』を連想させることに気づきます。
漫画『ガラスの仮面』との類似点

喜久雄、俊介、そして、自身も一流の歌舞伎役者でありながらこの2人の才能を見出し指導する、渡辺謙演じる花井半二郎の3人の関係性は、『ガラスの仮面』を彷彿とさせるのです。
喜久雄は「才能だけでのし上がった人物」であり、俊介は「生まれながらの梨園の御曹司」です。半二郎の指導のもと、互いに高め合い、時に傷つけ、時に分裂していく過程は、『ガラスの仮面』の主人公・北島マヤと、ライバルである姫川亜弓、そしてその二人を育てる大女優・月影千景の関係に似ています。喜久雄はマヤであり、俊介は亜弓であり、半二郎は月影に当てはまります。
半二郎は劇中で喜久雄を「生まれながらの女形やな」と評価する場面もあり、出会った当初から才能を認めていたところも似ています。
きっと、半二郎は15歳の喜久雄の演技を観た時、俊介は自分の代わりに「曽根崎心中」のお初を演じた喜久雄を観た時、かの有名なセリフ「おそろしい子!」と心のなかで唱えたかもしれません。

マヤは、その圧倒的な才能ゆえに、しばしば他の劇団員から嫌がらせを受けます。劇中『夜叉姫物語』という演目の「トキ」を演じる際、饅頭を食べるシーンで、饅頭が泥団子に代えられていたという陰湿ないじめに直面します。
しかし、役になりきるマヤは、それが泥団子であることに気づきながらも、芝居を貫くために食べてしまうのです。この名シーンは、マヤが芝居のためなら、自分の身体さえ犠牲にすることを厭わない執念を示しています。
喜久雄も同様の執念を持った人物です。彼は「日本一の歌舞伎役者にしてほしい。その代わり他のもんは何にもいりません」と悪魔と契約したと、自分の娘の前で宣言するほどです。
娘からしたら、自分も母もいらないと父親に面と向かって言われたのと同じことなので、傷つけてしまうことは容易に想像できるでしょうが、喜久雄は「芸」にしか興味がないためこの言葉を笑顔で伝えてしまう狂気性もあります。
このように目標達成のためなら、人間関係の悪化や激しい稽古による身体的な苦痛さえも厭わない喜久雄の姿勢は、まさにスポコン漫画の主人公そのもの。やはり、喜久雄はマヤなのです。
歌舞伎役者が観た『国宝』
ここで、もうひとつの視点を加えてみます。
『国宝』という映画をフィクションではなく「生活」として捉える、数少ない人たちがいます。それは歌舞伎役者たちです。彼らにとって、この映画に描かれた世界は、遠い物語ではなく、自らが生きる現実そのものです。
市川團十郎は自身のYouTubeチャンネルで『国宝』を語った際、特に印象に残ったシーンとして、屋上で自暴自棄になった喜久雄が酒を飲みながら落ちかけた白塗りメイクのまま舞う場面を挙げ、「映画『ジョーカー』のような精神的深みを感じ取った」と話しています。


インターネット上に数多ある『国宝』のレビューの中にも、喜久雄に『ジョーカー』を重ねたという声が多く見受けられます。確かに、屋上での場面は、映画『ジョーカー』で描かれた精神的な破壊と狂気を想起させるものがあります。
しかし、喜久雄は闇に堕ちるも完全には壊れず、人間らしさを失わない点で、アーサーとは異なる軌跡を歩みます。
アーサーになく、喜久雄にあるもの
では、アーサーになく、喜久雄にあるものとは何か。
『ガラスの仮面』と『ジョーカー』を引き合いに出すと、それぞれの主人公にはなく喜久雄にあるものが見えてきます。
まず、マヤとアーサーの違いを整理してみます。マヤは芸のためならすべてを犠牲にする人物です。泥団子を食べてでも役を貫く。その執念によって、マヤは「北島マヤ」という個人を消し去り、完全に役へと変身していきます。自分を捨てることで芸を極める。それがマヤの道です。
一方、アーサーは社会から拒絶され続けた末に、精神的に崩壊していきます。彼は「アーサー・フレック」という人間を捨て、「ジョーカー」という狂気の存在へと堕ちていく。そこに芸を極めるという目的はなく、ただ壊れていくだけ。
では、喜久雄はどうか。
喜久雄はマヤのように芸への執念を持っています。「日本一の歌舞伎役者になる。その代わり他のもんは何にもいりません」と悪魔に魂を売ったと宣言するほどです。しかし喜久雄は、マヤのように自分を完全に消し去ることはしません。
また喜久雄は、アーサーのように崩壊の淵に立つ瞬間もあります。屋上で白塗りのまま自暴自棄に舞うあの場面は、壊れかけた人間の姿です。しかし喜久雄は、アーサーのように狂気に飲み込まれて終わることもありません。
喜久雄は、壊れそうになりながらも踏みとどまり、また舞台に立ち続けます。芸に身を捧げながらも、人間としての感情や関係性を完全には捨てきれない。その不器用さ、その揺らぎこそが、喜久雄という人間のリアルさなのです。
つまり『国宝』は、「芸のために自分を消し去る」マヤの道でもなく、「自分を失って崩壊する」アーサーの道でもない、その狭間で揺れながら芸に命を懸ける人間の姿を描いた作品です。完全な変身も、完全な崩壊もしない。自分らしさを保ちながら、芸を追い続ける。命がけで。その生き様が、私たち凡人の胸を打つのだと思います。
天才と凡人をつなぐ「挫折」の感情
これまで映画の構造や喜久雄のキャラクターについて言及してきましたが、この映画が特に力を込めているのは喜久雄、俊介、半二郎の「挫折」する場面だと感じました。そして、そこが3時間に及んで展開する物語で私たちに感情移入させ繋ぎとめることに一役買っていると思うのです。
この映画、常に誰かが挫折を味わっている。
喜久雄の場合、自らの才能で歌舞伎の世界でのし上がるも、途中半二郎という後ろ盾が無くなった瞬間に地位はあっけなく転落します。いくら芸を磨いても後ろ盾ひとつでポジションが決まってしまう。人生は案外「そんなもの」だったりすると、観客は共感したのではないでしょうか。
俊介の場合、血筋は勝るが、芸で劣るという挫折があります。自分の代わりに「曽根崎心中」のお初を演じた喜久雄を観たとき「これまで通り同じ釜の飯を食いながら、同じ稽古をしていては差が埋まることはない」と悟り、現実に絶望し、自らドサ周りに出かける。そして8年後、力をつけた俊介は喜久雄にまた迫っていく。その復活の予感を「う、ら、め、し、や」と歩きながらつぶやく姿によって連想させ、「たとえ挫折しても人生のチャンスは一度きりではない」と希望を見出した観客は多いのではないでしょうか。
さらに半二郎は、「曽根崎心中」という大舞台を前に事故に遭うという予期せぬトラブルにより、代役を立てなければならないという現役の歌舞伎役者としての挫折を味わいます。また、指導者としては喜久雄と俊介という相反する二人の才能と血筋を育てながらも、最終的にはどちらをも完全には救えなかったという挫折があります。また、父親としても自らの決断により結果的に俊介を追い込んでしまった辛さ、無力感も挫折のひとつと言えます。ただ、この「俊介を追い込んだ」という見方について、2回目に『国宝』を観たあとで考えが変わりました。
2回『国宝』を観たときに、端的に言えば「半二郎は芸に優れた喜久雄を選び、俊介を捨てた」という印象を持っていたのですが、ネットで歌舞伎や『国宝』について調べていると、劇中で喜久雄と半二郎が演じた「連獅子(れんじし)」という演目が、物語の中で深い意味を持っているという解釈を目にしました。
「連獅子」とは、親獅子が子獅子を谷底に突き落とし、自力で這い上がってきた子獅子だけを認めるという物語です。半二郎が事故で倒れ、「曽根崎心中」の舞台に立てなくなったとき、代役として指名されたのは実の息子・俊介ではなく、喜久雄でした。寺島しのぶ演じる俊介の母・幸子は激しく憤ります。「なぜ実の息子ではなく、よその子を選ぶの?」と。
母は血筋を優先し、父は芸の才能を優先する。一見するとそう映ります。しかし、これは半二郎が俊介へ行った「連獅子」で、環境にあぐらをかいている我が子に苦しい試練を与えて一人前の歌舞伎役者にしようとしている、という解釈でした。私はこの見解を聞いて、俊介のキャラクターがわかりやすく「道楽息子」だったことに納得し、メインで語られることはなかった半二郎と俊介の親子のドラマが静かに流れていることに感激しました。『国宝』は、そういう重層的な物語でもあるのです。
喜久雄、俊介、半二郎。三人それぞれの挫折を追いかけていくと、この映画が描いているのは単なる悲劇ではなく、人生という現実そのものだと気づきます。
私たちの日常も、常に小さな敗北と挫折に満ちています。テストに落ちる、試験に失敗する、恋人に振られる、出世争いに負ける——それは喜久雄と俊介、半二郎の敗北と本質的には変わりません。
ここにスポコン漫画同様の楽しみ方があるのです。スポコン漫画では、主人公たちの挫折や敗北こそが物語の要であり、その試練を乗り越え、何度も立ち上がる過程に感動があります。『国宝』も同じように、三人の何度も繰り返される挫折と、それでもなお舞台に立ち続ける執念が、観客の心を揺さぶるのです。
ただし『国宝』が異質なのは、彼らの敗北が“命がけ”なゆえに美しく、鮮烈な点です。凡人の敗北は日常に埋もれ、やがて忘れられる。しかし、彼らの挫折は芸事に直結していて、その美しさと迫力が、見応えがあり観客を何度も劇場へ足を運ばせるのです。
芸か血か。どちらに恵まれても地獄
喜久雄は圧倒的な才能を持ちながら、血筋がないがゆえに常に不安定な立場に置かれます。俊介は血筋に生まれながら、才能で喜久雄に劣る苦しみを味わいます。この二人の人生を客観的に観ると、芸に恵まれても、血に恵まれても地獄を味わっているように思えます。俊介においては、「血」により糖尿病に侵され「芸」か「命」という究極の選択に迫られ、「芸」を選択する。そして、その様子を喜久雄は見届けます。
二人に迷いはなく、命さえ差し出せるのが「芸」なのでしょう。
芸を極め、芸の道を進み続けることは、まるで地獄のなかで蜜を舐め続けるような凡人には到達できない快感さえ伴うのかもしれません。こんな日常生活では、考えたこともないような「天才」が見える景色や感情がフッと匂うことがある。これがこの映画の面白いところです。
「あんな風には生きられねぇよな」、でも……
「あんな風に生きられねぇよな」というセリフは、三浦貴大が演じる竹野が放つ一言です。
この一言こそが、この映画を観た多くの人々の心に深く刺さる言葉だと思います。彼らの舞台を最も近くで見守りながらも、決してその世界に入ることのできない人。喜久雄にも、俊介にもなれない凡人が竹野であり、また私たちなのです。
できることなら私たち凡人も、彼らのように狂いたいのです。命がけで何かに執着し、すべてを賭けて生きてみたい。でも、狂えない。そこまで純粋に、そこまで絶対的に何かを求めることができないのです。
喜久雄と俊介は、私たちが見たくても見られない景色を知っています。喜久雄があの景色を探しているように、私たちも『国宝』を通して、命がけで生きる生々しい鮮やかさが観たい。その渇望こそが、私たちを何度も劇場へ足を運ばせるのではないでしょうか。
こうして振り返ると、『国宝』がこれほど人を魅了する理由が見えてきます。
それは、日本人にとって親しみやすい「スポコン」的なストーリーを、「歌舞伎」という、特に若い世代には馴染みの薄い異世界で展開した意外性にあるのだと思います。
スポコン漫画は、古くは『あしたのジョー』『巨人の星』、そして『スラムダンク』など、主人公が挫折を経験しながらも根気強く練習を続け、最終的に目標へ向かっていく過程が描かれ、長く人気を博してきました。
『国宝』も同じように、登場人物に自分を重ね合わせながら楽しむことができます。しかし、実際には喜久雄にも俊介にもなれない凡人である私たちだからこそ、彼らの「命がけで生きる喜び」がより一層胸に響き、何度も観たくなるのではないでしょうか。
狂いたくても狂えない凡人のために、「命がけで生きる美しさ」を教えてくれる。この映画はそのために存在しているのだと思います。その切実さと普遍性が、『国宝』という作品の深い魅力なのです。
本記事で紹介した映画

国宝
主演 吉沢亮
監督 李相日
「100年に1本の壮大な芸道映画」
——吉田修一(原作者)
画像引用元:Filmarks
※ 本ページはアフィリエイトプログラムによる収益を得ています
本記事で紹介した作品の原作

国宝(上・下巻)
吉田修一|朝日文庫
※ 本ページはアフィリエイトプログラムによる収益を得ています
※ 購入先リンクの飛び先はいずれも「上巻 青春篇」です
#宣伝会議田中泰延クラス 『国宝』week!
本記事は、2025年に宣伝会議で開催したライティング講座【「お金を払ってでも読みたいことを、自分で書けばいい」と思える書く力の教室】の最終課題「映画『国宝』のレビュー記事」を、「街角のクリエイティブ」掲載にあたって編集したものです。「#宣伝会議田中泰延クラス 『国宝』week!」と題して、これから8名の受講生の記事を1日1名ずつ順番に公開していきます。
玉絵ゆきの
美容/インタビュー/映画
![]()
![]()
美容ライター/web&書籍(これまで10冊経験)/フリーランス/インタビュー実績多数/【連載】LOCARI他。