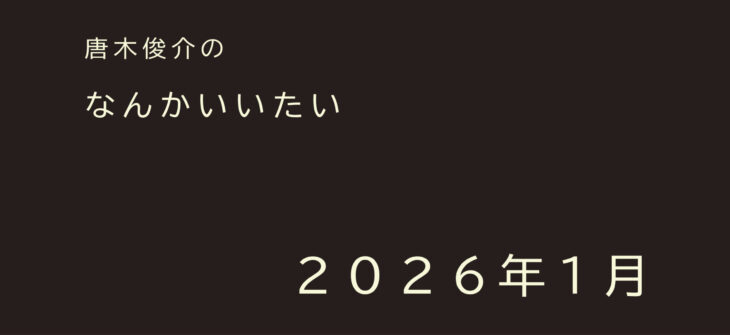ほとんどの国でカップ麺は「当たり前の食事」として定着したが、そのあり方は日本と世界で大きく異なる。
これは日本人という国民性によるものなのか、それとも「リアリティを追求しないと気が済まない企業姿勢」の表れなのか。
理由は定かではないが、とにかく今日はそんな話をしたい。
* * *
僕は仕事柄、海外出張が多い一方で、日本を訪れるクライアントを迎えることも多い。
日中の長いミーティングを終え、トーキョーでのディナーを共にして別れたあとは、彼らにとってのようやくの自由時間である。
その後どんなナイトライフを過ごしているのかは知らないが、あるクライアントは、ホテルへ戻る途中でコンビニに立ち寄るのを楽しみにしているという。
棚に並ぶ商品の中で、特に自国と違うと感じたのがカップ麺らしく、日本ではその種類もレパートリーも膨大なことに驚いたそうだ。
その中から1番美味しそうなパッケージのものを選び、ホテルで食べようとしたところ、これがかなり大変だったという。
お湯を注ぐだけで完成するはずのカップ麺なのに、蓋を開けると何種類もの小袋が出てきて、色分けや番号まで振ってある。
作り方の説明は小さな文字でぎっしり。日本語が読めない彼らは結局、すべての袋を一度に入れて食べたそうだ。
最初は「ラーメンのフィギュアを買ったのかと心配になった」と真顔で言われ、僕は思わず笑ってしまった。
* * *
確かに海外で販売されているカップ麺は、いわば「世界標準」の日清カップヌードルのように、お湯を注ぐだけで完結するタイプが主流だ。
タイやベトナムでは、稀に小袋が一つだけ入っていることもある。
真っ赤な液体が入る透明の袋は、見た目からして香辛料とわかりやすく、袋にも警告マークや注意書きが印字されている。
僕がまだベトナムに慣れていなかった頃、ホーチミンのホテルでその小袋を全部入れて食べたら、想像を絶する辛さで、帰国までの一週間ほど体調を崩したことがあった。
それでも、シンプルなカップ麺は説明書きを読む必要などほとんどない。

つい先日、何年ぶりかでカップラーメンをコンビニで買って食べた。
特にこだわりもなく選んだ一品を開けて驚いたのは、昔クライアントが言っていた通り、小分け袋が5つほど入っており、さらに作り方が細かくびっしりと書かれていたことだ。
しかも、カップの側面には「作り方動画」や「マニュアルPDF」へ飛べるQRコードまで付いている。
「そこまでしてユーザーに“理想の一杯”を作らせようとするメーカーの執念」がすごい。 手順の最初には、こう書いてあった。
まず、麺を水でほぐしてください。
簡単には食べさせないぞという、下準備がすごい。
見習い修行1日目。
僕が選んだのは生麺タイプというモノらしいので、最初にほぐさないと、固まってしまうらしい。
麺をほぐした後、お湯を注ぐ前に小袋を次々に開けていたら、よく読むといくつかの袋には「今開けるな」と書いてあった。
もう遅い。
結局すべての袋を投入して、待つこと5分。
* * *
日本人はいつの間にか、マニュアル文化――つまり「説明書きを読む文化」を身につけた。
もちろんそんなの読まないヨという人もいるだろうが、メーカーの意図通りにキチンと作ろうとする、辛抱強い人種であることは間違いない。
IKEAのイラストだけの取扱説明書が「わかりにくい」とネタにされるのは今や定番だが、思えばTAMIYAのプラモデルやラジコンのトリセツは、すべての部品イラストが原寸大で、世界一わかりやすい説明書と言われていた。
* * *
考えるに、カップラーメンの真髄は「誰でも作れる」ことにあるのではないか。
海外の人々は、カップ麺に取扱説明書を期待しないし、おそらくあっても読まない。
最初から海外のカップ麺は、みずからをカップ麺であると自覚し、わきまえている。
これは美味しい・不味いの話ではない。
“カップ麺というカテゴリーに誇りを持ち、ホンモノを超越しようとしない潔さ”の話だ。
日本のカップ麺はもう少し、そのあたりをわきまえるべきかもしれない。
――そう思い至ったころには、とっくに5分を過ぎていた。
* * *
実は昔、「昨今のカップ麺はどんどん生意気になっていて、人様に命令するようになった。黙れ。黙りなさい。カップラーメンたるもの、いつの日もカップラーメンであれ」というエッセイを読んで大笑いしたことがある。
自分もまさにその体験をした訳で、それ以来、古本屋やネットで作品や著者を探しているのだが、いまだに見つからない。
もしご存じの方がいたら、ぜひ教えてほしい。
田所敦嗣さんの著書

スローシャッター
田所敦嗣|ひろのぶと株式会社
※ 本ページはアフィリエイトプログラムによる収益を得ています。
田所敦嗣
エッセイ
![]()
![]()
千葉県生まれ。水産系商社に勤務。エッセイスト。著書 『スローシャッター』(ひろのぶと株式会社)で、SNS本大賞「エッセイ部門」受賞(2023年)。フライ(釣り)、写真、野球とソフトボールが趣味。人前で声が通らないのがコンプレックス。

 更新日: 2025.12.25
更新日: 2025.12.25