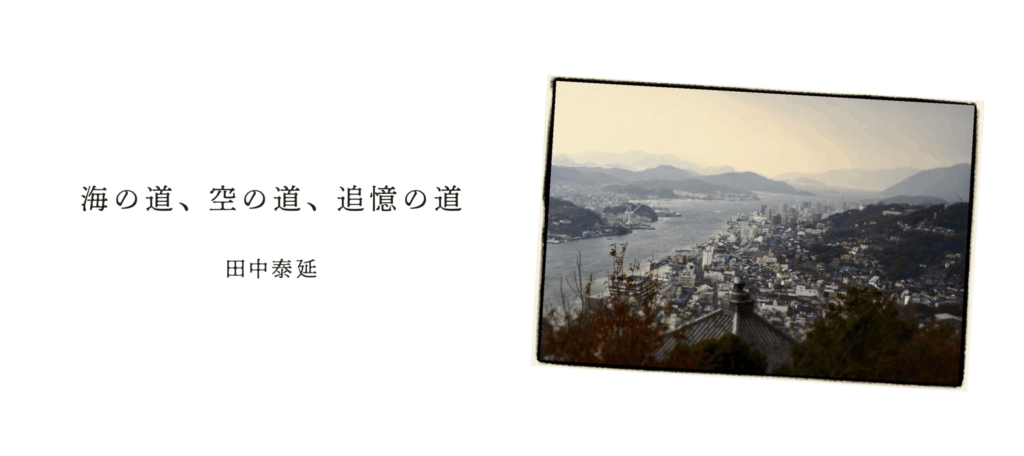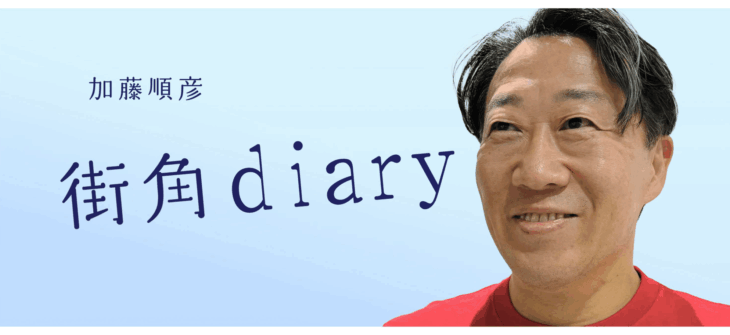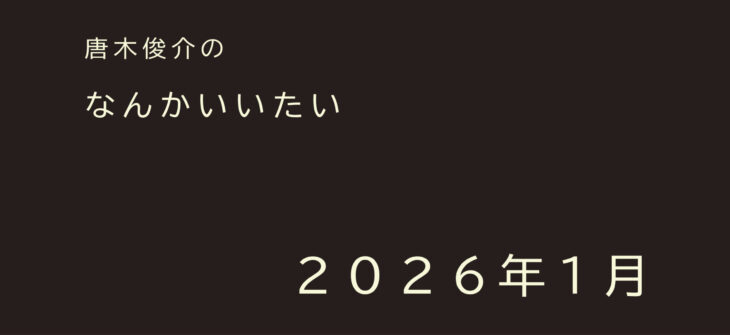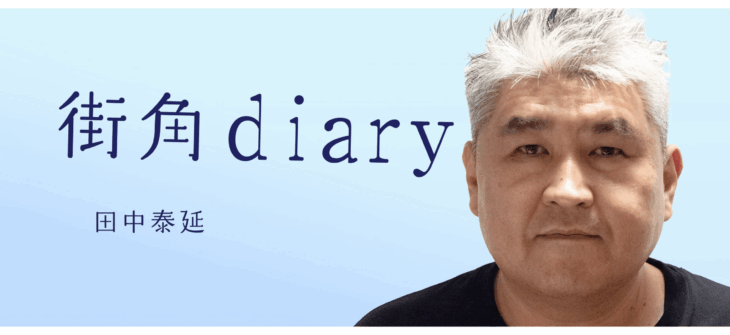獲ったど〜〜〜〜!!!

初の海釣りで
アコウ(キジハタ)
獲ったど〜〜〜!!!

ここは、広島県・尾道市から船を出した瀬戸内海。私は生まれて初めて、海釣りをしています。
こんにちは、ひろのぶと株式会社の廣瀬翼です。
普段は編集のお仕事をしています。いるのは陸地、前にするのはPC、手に握るのは鉛筆……が日常の私が、海釣りを体験することになりました。
きっかけは、当社代表の田中泰延が、尾道で天然真鯛を贅沢にドーンと使った鯛の炊き込みご飯の素を製造・販売している「おのみち鮮魚店」の鈴木創介さんから、尾道取材のご依頼を受けたこと。
ここにも一つの長いドラマがあるのですが、そちらはどうぞ、田中がおのみち鮮魚店さんに寄稿した『海の道、空の道、追憶の道』をご覧ください。
まあ、紆余曲折ありまして。この2025年3月、ひろのぶと株式会社の一同で尾道に伺うことになりました。
取材にあたって、私たちから鈴木さんにこんなお願いをしました。
「もし、もし、万が一億が一で叶いましたら、鯛の漁を見学できないでしょうか」
さすがに実際の漁の見学は叶いませんでしたが、鈴木さんはすぐに
● 漁から戻ってきた漁師さんとお話しする時間
● プレジャーボートでの海釣り体験
をご用意くださったのです。
ということで、今回は普段コンクリートジャングルで電子画面ばかり見つめている廣瀬が触れた、尾道の海についてお届けです。
まずは海釣り体験から少し時間を遡って、その前日。漁業協同組合の組合長をされている漁師・藤川伸一さんに伺った、尾道の海と鯛と漁の話からはじめましょう。
* * *
緩やかな潮と、豊かな海の栄養。潮を読み、じっと待つ。

鈴木さんの案内で港の駐車場に到着すると、船着場には漁から帰ってきたところの船が。泰延さんがいち早く向かい、船上で作業をしていた漁師さんに挨拶をします。

藤川伸一さん。尾道漁業協同組合の代表理事組合長を務める、この道40年以上の漁師さんです。
鈴木さんは「おのみち鮮魚店」を立ち上げた時から、鯛を藤川さんから仕入れています。泰延さんは3年前に尾道を訪れた時も、藤川さんにお話を聞いていたそう。

「久しぶりやねぇ」

「はい、3年ぶりで」(泰延さん)

「もう3年ですか。もっと最近なような気がするけどねぇ」
少し気難しそうな職人の空気をまとう藤川さん。すでにお話をしたことのある泰延さん。なんとなく、私は間に入ってはいけないような気がして、一歩離れたところから耳を傾けながら写真を撮ることにしました。

「それで、今日は何匹?」

「2匹でお願いします」(鈴木さん)
藤川さんが、船上の生け簀から鯛を見繕います。今日の天気や近隣のお店の話なんかをしながら、海水を入れたバケツを用意。鉤型の道具で鯛の目の斜め上をひと突きすると、そのままバケツに入れます。


「魚ってこうやって締めるんですね」
その鮮やかな手際を見ながらポツリとつぶやくと、藤川さんが手を止めることなく教えてくださいました。

「人間でいうところの、こめかみやね」
魚にもこめかみがあるのか、と思いながら藤川さんの手捌きに見惚れている私に、鈴木さんが加えてくれます。

「藤川さんがやっていると簡単そうに見えるんですけど、これがなかなか刺さらないんですよ」

「まあね、そりゃもう、45年 漁師しよるからね」
藤川さんの表情が、少し照れくさそうにほころびました。そのまま2匹目を選びます。

「これは1.5kgくらい」


「うわぁっ、大きい」

「皆さんには、もう一回り小さいほうがええかな。1kgくらい。それでも、いつも鈴木さんが持っていくのより大きい」

「本当ですね」

「ちょっと肥えとって」
藤川さんが、今度は1kgの鯛を締めてバケツに入れます。血抜きを待つ間、鯛や尾道の海について伺いました。

「さっきの大きい(1.5kgくらいの)鯛で、何年ぐらいであの大きさになるんですか?」

「3年半ぐらいかな、わからんけども。
鯛は肉食でね、イカとかタコとかエビとか、そういう生きたものばっかり食べる。だから、早いんよ、大きなるのが。
それで、泳ぐんじゃろうね、鯛は。チヌ(クロダイ)より、よう回遊する」

「獲ってくる場所でも違うって言いますよね」

「まあ、場所によって、痩せとるとか、デカいとか、まん丸とか、あるね」
ほうほう。話を聞いているうちに、一歩引いていたはずの廣瀬の好奇心スイッチが一気にONになります。

「尾道のお魚が美味しいのは、海が穏やかだとか、そういう環境があるんですか?」

「どうなんかね。でも、あれでしょうね、魚が食べるエサが違うんでしょう。
やっぱ、魚というのはエサがないと来んけえね。たとえば、『去年ここにおったんやけど』というところも、もしそこにエサがなかったら来んからね」

「ええ、ええ」

「それから、潮の流れがあんまり速すぎても良くないね。潮が速いと身が締まるというけれど。たとえば、同じ瀬戸内海でも明石の鯛と尾道の鯛とは、体つきが違う」

「ああ、そうですね」

「尻尾の付け根がね、尾道の鯛は丸なっとるじゃろ? 痩せとる鯛はここが細い」

「へー!」

「ほんとだ、太い」(豪さん)

「肥えとるかどうかを見るのは、背中の丸みと尻尾。尻尾のつなぎ目」



「季節による違いもあるんですか?」

「まあ、今(3月上旬)が一番美味しいです。1月、2月、3月。それ以降は水温が上がってくると、よう泳ぎ出す。これから産卵の季節に入ってくる」
そう言いながら、藤川さんが生け簀の中を指差します。

「今、魚たちがジーッとしとるやろ? 泳がんで」

「本当に、泳がないですね」

「水温が7〜9度。10度は切っとってね。これがええ」


「こういうふうに、ジーッとしとると、痩せんのでね。傷まんし。傷まん。魚同士で擦れたら鱗が剥がれてね、見てくれが悪いよね」

「ああ、そうなんですね」

「生け簀にこれぐらいの量なら酸欠になることもなかろうしね。
なーんか、うちの生け簀ではね、魚があんまり泳ごうとせんのよ。ジーッと落ち着いて。落ち着いていられたら、ストレスも少ないやろうしね」
温度計を使わずとも管理されている水温。それが、45年のプロの技。

「漁にはね、この網を使います」


「潮が止まった環境がいい。鯛は潮が止まると、浮く習性がある。上向いて。
この網は高さが2mあるんじゃけど、潮の流れがあると網が流れて寝るでしょう。そうすると、鯛が網の上から逃げる。潮が緩んどると、網が立つ」

「それで、鯛が網にかかりやすくなる、と」

「だから、潮の流れを見ながら時間を待たないとあかん」
そして、その潮を読んで待つ場所にも、漁師の腕が光ます。

「漁師さんは自分の漁場を人と共有しないんですよね」

「『ここが自分の陣地です』という……?」

「陣地いうか、暗黙の了解。占有権があるわけじゃないけぇね」

「ええ」

「ただ自分で魚がおるところを見つけるだけ。自分の経験で見つけたらいい。誰がやってもええんじゃけどね、暗黙の了解。
船が近くにないところへね、行くね。地元のもんでも、敵じゃけな」

「わはは」


「別の船がおったら、どんなにそこがええ場所でも、網を打たんわけよ。それで、他のいい場所に移動する。
そうやって自分の“いい場所”を何十ヶ所、100ヶ所、200ヶ所も持っとかにゃあいけん」

「『この辺りが漁のポイント』みたいなのを、いくつも」

「そうそう。人間の癖は治るけど、魚の癖は治らんからね。
魚の習性は絶対治らん。そこへ来るときは、絶対に来る。大きい鯛がいる時は大きいのばっかおる。小さいのが来るときは大きいのは来ん」

「そういうことなんですね」

「その習性と、潮の流れ。潮の流れを間違うたら、たとえ海の底に100匹おっても、1匹もかからん」
気がつけば、30分近くが経っていました。締めていただいた2匹をビニール袋に入れて受け取ります。

「美味しいものは、私が持つ!」と食い意地を張る廣瀬、ビニールを受け取り中を見て、思わず息を呑みました。

「鯛って、こんなにカラフルで綺麗なんですね……!」
知らなかったのです。スーパーに並ぶ鱗の取られた鯛しか見てこなかった私は、鯛が黄色や青、紫がキラキラと宝石のように散りばめられて輝く魚だとは。

驚く私に、藤川さんがにっこり笑顔で話してくださいます。

「鯛はね、青い星があるよね。点々がね。ちょっと紫色なんよね、紫に光る。
太陽の光に当てたら、ここのおでこの曲がりのところが紫にカーッと。それで、オスとメスでは色が違うけん」


「そうなんですか? この子たちは、どっちですか?」

「これ、メス。オスは黒いんよ」

「2匹とも、メス?」

「うん。それで、こっちがベッピンさん。大きくて、ピンク色」
その鯛に対する語り口は、まるで子供を見ているかのような目線を感じました。海と向き合って、魚が本当に大好きなんだなと、たった30分だったけれどもその厳しさと優しさのどちらにも触れられた気がしました。
藤川さんにお礼を言い、船着場から駐車場へ上がって行っていると、藤川さんが船から降りてきて泰延さんへ声をかけました。


「今回は、どのぐらい尾道にいはるんですか?」

「今日と明日の2日満喫して、明後日の朝から東京に戻ります」

「そうですか。皆さん、楽しんで行ってください。それで、また尾道にいつでも来てくださいね。また、お会いしましょう」



※ 加納さんは撮影係に徹されておりました
受け継ぐ味、「尾道産 天然真鯛の炊き込みご飯」
藤川さんの鯛を手に、そのまま「おのみち鮮魚店」さんの事務所・厨房へ向かいます。そこで鯛を捌いてお昼にいただく。そんな贅沢です。

「藤川さんの鯛は、違うんですよね、美味しさが。
それから、同じ藤川さんの鯛でも、自分で厨房で締めるのと藤川さんに締めてもらうのとでは、全然違う。
藤川さんに締めてもらうと、なんでかなぁ、すごく美味しいんですよ」
港からの車中で聞いた、鈴木さんの言葉。そこには、藤川さんへの絶大な信頼を感じます。
事務所に入ると、大きなシンクが2つあるキッチン台。ここで、実際に「尾道産 天然真鯛の炊き込みご飯」をつくる時と同じように、鈴木さんに鯛を捌いていただきました。
シンクにまな板をかけて水を流しながら、まずはエラを取ります。

続いて金属の鱗取りで、鱗をすべて取っていきます。これが、骨が折れる作業なのだそう。時々まだ活きのいい子がいて、バチンと跳ねることもあるのだとか。

取れた鱗の一枚一枚は、ほのかに紅がかった半透明。幻想的な花びらのようで、アクセサリーにできそう……と思って見ていたら、実際に鯛の鱗をレジンで固めてハンドメイド・アクセサリーにしている人もいるそうです。

鱗が取れたら、お腹を切って内臓を取り出し、水で洗い流します。

と、ここで……

「メスでした」

「藤川さんの言っていた通り!」

「パッと見ただけで……!」
続いて頭を切り落とし、鯛の身を3枚におろします。頭は、そのまま出汁を取るアラに。そして半身は贅沢に「天然 真鯛の炊き込みご飯」に使います。
「いやあ、人に見られながらやると、いつもとは違う緊張をしますね」と汗を流して笑う鈴木さん。でも、きっと私たちがいなかったとしても、同じように汗を流しているのだろうと想像できる、たいへんな作業です。

「『尾道産 天然真鯛の炊き込みご飯』は、1日にどれくらいつくれるんですか?」

「捌けるのが頑張って10匹ぐらいだから、20セットですね」
鈴木さんと奥さまがすべて手作業で用意されている「尾道産 天然真鯛の炊き込みご飯」。その味付けは、鈴木さんの伯母さんが観光遊漁船で振舞っていた人気メニューを再現しています。でも、この“再現”がなかなか大変だったそうで……

「伯母がつくるときは、どの調味料も目分量なんです。本人に聞いてみても『醤油はドポポ、ぐらい』みたいな感じで(笑)。
でも、商品として出すにはちゃんと計って決めないといけない。
あとは、ご自宅で手軽につくっていただけるよう、冷凍でお届けして、ただ炊飯器に入れるだけにするためのことも考えて、つくっていく必要もあります。
何パターンくらい試したかは、もう覚えてないですね(笑)」
楽しそうに笑って話す鈴木さんですが、きっとゴールの見えない試行錯誤を繰り返されたんだろうなと感じました。
そんな話をしているうちに、「ピーピー」という炊飯器の音と共に、芳醇な鯛の香りが部屋に広がってきます。


さあ、いよいよ尾道の海の恵みを贅沢にいただく鯛づくしのお昼ご飯です!




うまいうまい、美味しい美味しいとひたすらに食べ続ける、ひろのぶと株式会社の4人。すべてのお皿がペロリと綺麗になくなったのを見て、鈴木さんは驚いていました。
成長期(横)の娘が2人いる我らを舐めたらいかんぜよ!(※ ひろのぶと株式会社で編集をはじめて5kgほど増量しました)
小さき命が弾ける水面、たゆたう時間と引き上げる命。
ということで、時間は冒頭に戻りまして、「ひろのぶと、おのみちへ行く。」3日目の朝。今度は、瀬戸内の海で自分たちが魚を釣る体験をしています。



プレジャーボートを出してくださったのは、鈴木さんの弟さん。企業にお勤めですが、尾道とおのみち鮮魚店の取材に東京から私たちが来るという話を聞いて、「それは大切や!」とお仕事を調整してご対応くださったそうです。本当にありがとうございます。

集合は、朝7時。まだ寝ているのか起きているのか定かではないような細目の私でしたが、鈴木さんと弟さんは私たちが港に着いた時には船の準備を済ませていて、朝日のようなハツラツさで「おはようございます!」。
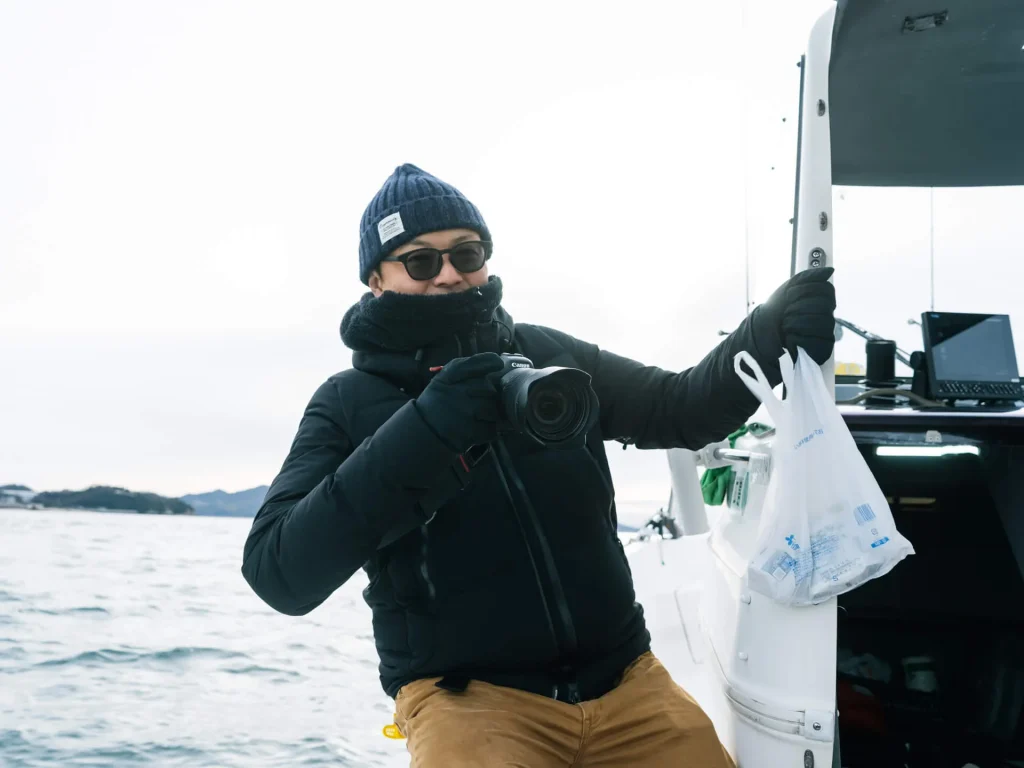
……本当に同じ人間でしょうか……?! だって、鈴木さん、前日は私たちと同じ行動をしている、どころか、ご自宅に帰られるので近くのホテルに泊まる私たちよりも寝るのは遅く、起きるのは早いだろうに、なぜこんな爽やかなのか?!
そんな頼もしいお二人の案内で船に乗り込み、見たことのないタイプのライフジャケットを装着します。いよいよ、ボート出発です。

釣りスポットまでブオーッと駆けるボート。心配していたお天気も、次第に晴れ間が見えてきました。



いくつもの橋が見え、いくつかの橋をくぐりました。鈴木さんはそのすべてを「〇〇橋です」「〇〇島と〇〇島を結ぶ」と説明くださったのですが……全部、写真に撮ったけど、どれがどの橋か全然覚えられていません、ごめんなさい!



ボートがスピードを緩めたところで、海をのぞいて泰延さんがつぶやきました。

「この水面に見える小さな白いプツプツ、全部プランクトンなんやな。ほんまに、栄養豊かな海なんやな」

その言葉に、なぜか元気が湧いてきます。
ボートが止まり、ついに釣りタイム。竿に擬似餌で挑みます。

これまでやったことがあるのは、渓流釣り堀のみ。海釣りも、ハンドルでクルクルと糸を巻き上げる竿も、私は初体験です。鈴木さんの弟さんがほぼほぼマンツーマンで竿の扱い方を教えてくださいます。

この竿が、とてもよくしなる。あまりにしなるものだから、最初から釣れたのではないかと思ったほど。でもそれは、海水の重みのようでした。

説明によると、大切なのは擬似餌が海底に軽くついたところから、ゆっくりと巻き上げていくこと。巻き上げるスピードは一定で、ハンドルを握った左手が綺麗な円を描けていると良いそうです。
同じペースで、クルクル回す……焦らない……
それはどこか、禅のような、あるいはコーヒーを淹れている時のようなリラックス感があって、ふわりと頭が軽くなっていきます。頭の中をゴミ掃除しているような。
あ、これは……もし釣れなかったとしても、楽しいし気持ちいい……そう感じはじめたところで、ボートを移動させることになりました。

次のスポットでも3回ほどチャレンジしたら、また移動。3〜4回チャレンジして移動の繰り返し。釣りって、もっと忍耐強く1ヶ所で我慢し待つものだと思っていたので、意外と移動が多いことに驚きました。
弟さんは、レーダー探知機を見てスポットを定めていきます。

「レーダーはバチバチに反応しとるんですけどね。昨日までの雨で水温下がっとるから、動かんのかなぁ……釣れてくれ……!」
そう言いながら、少しでも釣れる可能性が高いところを探してくださいます。
この便利なレーダーがなかった時代の漁師さんはどうしていたか。経験でよく釣れる場を見出し、島の山と山を線で結んで場所を覚えていたそうです。昨日聞いた藤川さんのお話がよみがえります。

スタートから1時間弱。私の手つきを見て、弟さんが声をかけてくださいました。

「おお、いいですね! 綺麗な円が描けてますよ、あとはそれで釣れてくれるだけ……釣りは、魚と人間の化かしあいですからねぇ」
自分では最初と今の違いがいまいち分からないのですが、やっぱりうれしいもの。が、ここで調子に乗るとスピードが上がるから平常心平常心……と言い聞かせます。
とその時、背後から「かかった!」という声が。振り返ると、豪さんがカサゴを釣り上げていました。

これで成果0ではなくなったと安心していたところ……
ピクッ
かすかに感じた、さっきまでとは何か違う動き。

「きた……かもです!」
バッと鈴木弟さんがこちらに寄り、竿と糸を見て「かかってます!」。連続の釣果の兆しに、ボート全体が湧きます。
絶対逃さないぞ、食い逃げされる前に巻き上げねば……! と、さっきまでの禅モードは何処へやら、力一杯巻き上げようとしたら……

「焦らない、焦らない、さっきまでと同じようにゆっくり、丁寧に」
頭の中は「?」。だって、早く上げないと逃げられちゃうんじゃ……と思いながら、言われた通りゆっくりと巻き上げます。途中、軽くなった感覚がして「逃げられたかも」と思ったのですが、鈴木弟さんは竿と糸を見ながら「大丈夫です、まだいます」。全然わかりませんが、信じてゆっくり巻き上げ続けます。そして……


獲ったど〜〜〜〜!
と、またも後ろでも「かかった!」の声。なんと豪さん、本日2度目。二人ともアコウ(キジハタ)を釣り上げました。これでお昼ご飯も安泰です。

その後、豪さんがもう1匹アコウ(キジハタ)を釣り上げ、海釣りタイムは終了。豪さんばっかりたくさん釣れて、魚も誰の言うことを聞かないといけないのかよくわかっていると見える。
尾道へ戻る途中。波が穏やかなところで、鈴木弟さんがボートを止めました。鈴木さんが理由を説明してくださいます。

「ここで一旦、『もう海には戻れんぞ』と、締めるんです」
鈴木弟さんがボートの開けたところに釣れた魚を持っていき、昨日藤川さんが握っていたのと同じような金具を持って、カサゴやアコウの脳天を突き刺します。

カサゴは固いし、アコウはでかい。しかもヌルッと滑る。だから少し大変そうでしたが、順調に締めて海水につけていきます。と、最後の一匹で……

「こいつ、怒っとる!」
魚が、怒る? どういうことなのか。

「こいつ、口を開いてくれんから握れんくて、締めれないんですよ」
そう言いながらも格闘の末、無事4匹すべてを締め上げました。

魚が「怒ってる」。妙にこの言葉が耳に残り、ぼーっと考えながら潮風にあたる帰りのボート。陸に戻ったのは11時ごろ。たびたび移動していてそんなに長いとは感じていませんでしたが、4時間も海の上にいたのでした。

尾道の命をいただくという恵み。
今日も釣れた魚を贅沢にいただくため、再びおのみち鮮魚店さんの事務所へ。鈴木さんと弟さんが4匹を捌き、煮付けとお刺身にしてくださいます。



私たちは何もお手伝いできることなく(しかし捌けと言われても捌けない)……ボートを出していただいてさらに至れり尽くせりです。鈴木さん、弟さん、本当にありがとうございます。
煮付けは、カサゴとアコウをドカンと入れて、豆腐を一丁。味付けはシンプルに醤油とお酒のみ。

「漁師めしです」というお二人。ちなみにお二人の伯母さんは、鯛の炊き込みご飯だけでなく、こういった煮付けをつくっても美味しいそう。弟さんは「あの人、手から出汁でとるんや!」と言っていました。

しかし、自分で釣ってきたお魚。なんだか少し愛着が湧いていて、捌かれるとちょっと胸の奥がクーンとします。
そもそもこのお魚は、美味しいご飯が食べられると喜んでパクッとしたら、知らない水上に持ち上げられて、そして食べられる……あれ、すごく残酷じゃない……?
そんなことをポロッとこぼしたら、豪さんも鈴木さんも泰延さんも笑って、「まあ、食べるって、そういうことだからねぇ」。

そこで、ハッとしました。ああ、これまで私は「魚」を、理屈では生物とわかっていても、限りなくただの「食べ物」「モノ」と捉えて接してきたのだと。
そしてきっと、鯛を「ベッピンさん」だと言った藤川さんは、魚が「怒ってる」と言った鈴木弟さんは、魚に「命・生き物」として触れて向き合い、その上で美味しくいただこうとしているのだと。
それがストンと腑に落ちた時、とても収まりの良い居心地で、尾道が、尾道の海が、尾道の人が、自分とひとつづきの有機的な存在として「好きだ!」と感じたのです。そうして、この時の「いただきます」は、いつもより3度、温かさが広がりました。

ちなみに、残酷だなぁと言っていたことが信じられないくらい、ヒレのゼラチンも目玉も全部を綺麗にペロっといただいた私たちに、「量が多くて食べきれないだろうと思っていたのに……?!」と驚いてらっしゃった鈴木さんと弟さん。
だから、成長期(横)の娘が2人いる我らを舐めたらいかんぜよ!(※ ひろのぶと株式会社で編集をはじめて5kgほど増量しました)
* * *
「尾道産 天然真鯛の炊き込みご飯」に欠かせない、漁師さんの力と尾道の海の恵みを体感した2日間。
最後に、なぜ鈴木さんは、組合長という立場で、さまざまな飲食店や関西の高級スーパーへ卸している人気の漁師・藤川さんから鯛を仕入れられるようになったのか、伺ってみました。

「本当に、そこが幸運だったなと思います。
もともと、漁師だった祖父母や伯父伯母のつながりで、知り合いではあったんです。
それで、おのみち鮮魚店を立ち上げようと考えていた時に相談したら、『若い人が地元に戻ってきて、尾道の魅力を発信しようとしているのなら、それに協力できるなら』と鯛を仕入れさせていただけるようになったんです」
尾道の居心地の良さは、「尾道産 天然真鯛の炊き込みご飯」の香りと味わいは、尾道の豊かな自然と、それを愛し生きる者として向き合う人々が生み出しているのだと、そう、感じました。
ね、きっと私、これから「尾道産 天然真鯛の炊き込みご飯」をいただく時には、鯛を「ベッピンさん」と言っていた藤川さんの笑顔と、汗を流しながら鯛を捌く鈴木さんの横顔と、釣りを丁寧に教えてくださった鈴木弟さんの声を思い浮かべるよ。

おのみち鮮魚店「尾道産 天然真鯛の炊き込みご飯」
関連ページ
Sponserd by

廣瀬 翼
レポート / インタビュー
![]()
![]()
1992年生まれ、大阪出身。編集・ライター。学生時代にベトナムで日本語教師を経験。食物アレルギー対応旅行の運営を経て、編集・ライターとなる。『全部を賭けない恋がはじまれば』が初の書籍編集。以降、ひろのぶと株式会社の書籍編集を担当。好きな本は『西の魔女が死んだ』(梨木香歩・著、新潮文庫)、好きな映画は『日日是好日』『プラダを着た悪魔』。忘れられないステージはシルヴィ・ギエムの『ボレロ』。